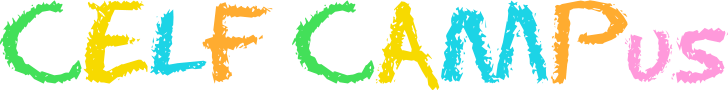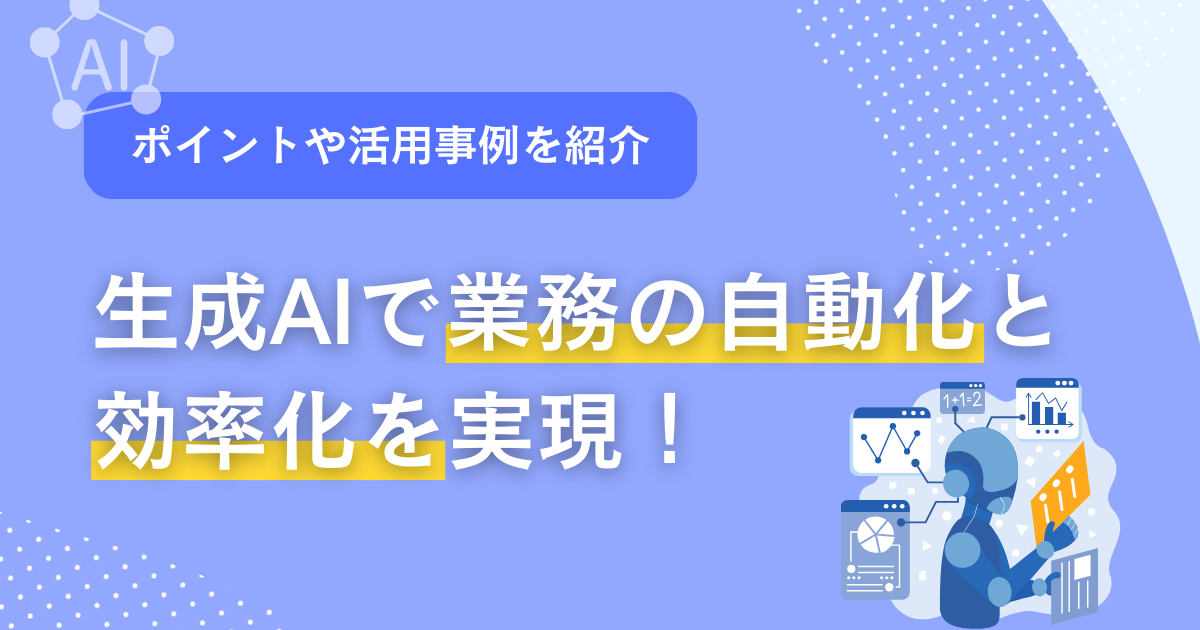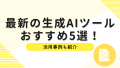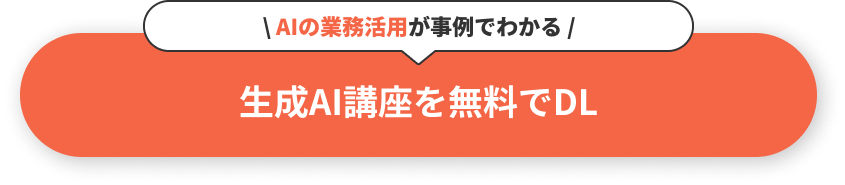近年、多くの企業で人手不足や生産性向上が課題となっています。課題解決への貢献が期待されている技術が生成AIです。生成AIは、資料作成やデータ分析などの業務を自動化できるため、業務効率化を可能にします。2022年のChatGPTの登場により、生成AIを業務に活用する動きが広がってきました。
本記事では、生成AIの概要や業務効率化の事例とともに、生成AIを導入する際のポイントや注意点について解説します。
生成AIとは?従来のAIとの違い
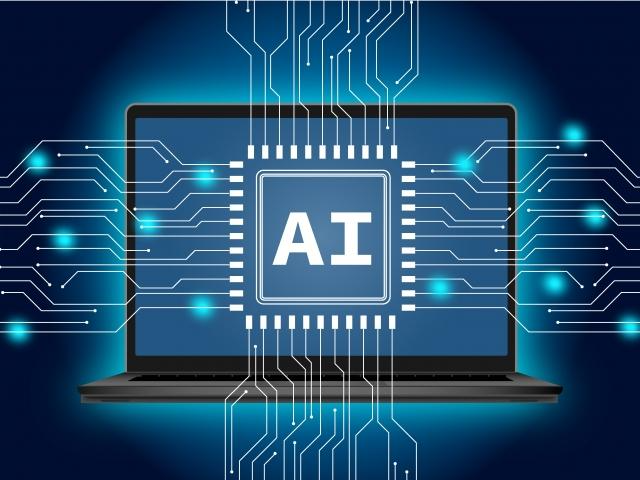
生成AIとは、文章や画像などのコンテンツを生成する人工知能の技術です。ジェネレーティブAI(Generative AI)とも呼ばれます。機械学習の手法「ディープラーニング(深層学習)」により、高度なコンテンツを創造する点が特徴です。
従来のAIは、主にデータ分析や予測を得意としていましたが、生成AIは学習したデータをもとに、簡単な操作で新しいコンテンツを容易に生成できます。
生成AIで自動化・効率化できる業務
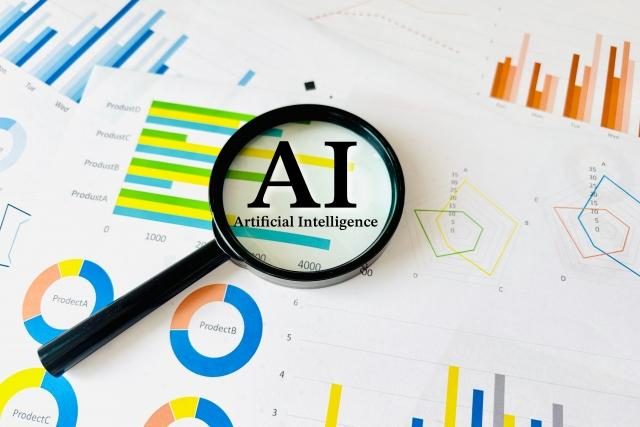
生成AIは、テキストや画像、動画、音声といったコンテンツの自動生成が可能です。生成AIを活用すれば、以下の業務の自動化・効率化が期待できます。
- 文書・資料作成
- スケジュール管理
- 問い合わせ対応
- 情報収集・データ分析
- マーケティング業務
- アプリ開発(プログラミング)
ここでは、それぞれの業務について解説します。
文書・資料作成
生成AIの活用により、会議の議事録や報告書、データレポートなどを短時間で作成できます。例えば、メールの返信文章を生成できるほか、音声認識技術を活用すれば、会議中の発言を文字起こしして議事録を自動生成することも可能です。
グラフやチャートの挿入も自動的に行えるようになり、作業時間の大幅な短縮につながります。定期的に資料作成が必要な職種では、業務効率化の効果を実感しやすいでしょう。
翻訳作業もできるため、文書作成にかかっていた時間の短縮が可能です。それにより、従業員はより重要な業務に時間を使えます。
スケジュール管理
過去のプロジェクト記録やチームのリソースを分析させることにより、効率的なスケジュール作成が可能です。企画立案からスケジュール作成、タスク設定や進捗管理まで自動化できます。
プロジェクトの進行がスムーズになり、チーム全体の生産性向上につながります。プロジェクトマネージャーが、より戦略的な業務に集中できる環境も整えられるでしょう。
問い合わせ対応
質問に自動返信するチャットボットやバーチャルアシスタントを導入すれば、顧客からの問い合わせに24時間365日対応できます。顧客は営業時間にかかわらず回答を得られるため、利便性が向上し、顧客満足度向上につながるでしょう。
企業側は問い合わせ対応を効率化でき、人的リソースの負担も軽減できます。負担が軽減されることにより、オペレーターはより複雑な対応や重要な業務に集中できます。
情報収集・データ分析
これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業も、生成AIで自動化できます。請求書のデータ入力や在庫管理システムの更新などの定型的な作業を自動化します。
Web上で公開されている幅広い情報源から、競合調査や消費者行動などのデータも収集可能です。短時間でデータを収集できるだけでなく、人では思いつかない角度からの分析も期待できるでしょう。
マーケティング業務
生成AIにより、ターゲティング広告の最適化や顧客データの分析が可能です。商品開発のアイデア出しや、企画立案などの独創性が必要な業務も対応できます。例えば、特性やニーズで顧客を分類し、各グループに合わせたキャンペーンの立案も可能です。
リアルタイムでの迅速な意思決定もできるため、適切なタイミングで施策を実行できます。新しい視点でコンテンツを生成できるだけでなく、マーケティング活動の精度が向上し、広告の費用対効果を高められます。
アプリ開発(プログラミング)
生成AIを活用すれば、プログラムを作成する際に欠かせないアルゴリズムの提案をはじめ、全体像の把握に役立つフローチャートの作成や、プログラミングコードの自動生成が可能です。完成後のバグ修正やテスト作業もでき、プログラマーや開発者は、生成AIが作成したコードやエラー結果をもとに調整する流れで業務を進められます。
専門知識がない場合でも、ツールを活用すればアプリ開発が可能になるため、アプリ開発のハードルが下がります。これまで担当者が手作業で行っていた業務の一部を自動化できるため、アプリ開発におけるエンジニアの作業負担を軽減でき、生産性の向上につながるでしょう。
生成AIで業務効率化を実現した企業事例
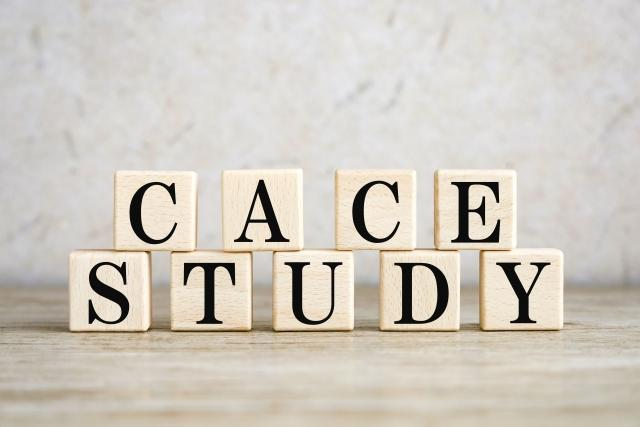
生成AIで業務効率化に成功した企業の事例を知れば、自社の参考になります。ここでは、株式会社ひだホテルプラザと株式会社プロカラーラボの事例を紹介します。
株式会社ひだホテルプラザ
株式会社ひだホテルプラザは、宿泊施設やレストランなどを運営する企業です。同社は、手書きのアンケート結果をスタッフが1件ずつ手作業で入力しており、入力工数の負担が課題となっていました。
ノーコード・ローコード開発ツールの「CELF」に搭載された「CELF AI」を導入し、AI-OCR機能を活用したところ、手書きアンケートをPDF化して自動で文字を認識・データ化する仕組みを構築できました。
また、蓄積されたデータを時系列で比較・分析でき、顧客の傾向やニーズの変化を継続的に把握できるようになったのです。さらに、CELFの集計・分析機能との連携により、手書き文書のデータ化から集計・分析までをワンストップで対応できる仕組みを整備しました。
その結果、入力工数の負担を軽減させただけでなく、顧客の声を迅速にサービス改善に反映できるようになっています。
参考:CELF AI
株式会社プロカラーラボ
株式会社プロカラーラボは、写真館向けにデジタル画像処理やプリントサービスを提供している企業です。同社では、写真を受け取った顧客からの問い合わせが日常的に多く寄せられていました。
しかし、これらは撮影元の写真館でなければ対応できません。そのことを案内するのに多くの工数がかかっていることが課題でした。そこで「CELF」を導入し「得意先一覧」や「問い合わせ履歴」などのデータを活用し、問い合わせを行った顧客の撮影元を特定しました。
該当する写真館の連絡先も自動で抽出し、過去の対応履歴をもとに、CELF AIが案内文や回答文を自動生成する仕組みを構築したのです。それにより、対応時間の短縮を実現し、業務効率化と顧客満足度の向上につなげています。
参考:CELF AI
生成AIを導入する際のポイント

生成AIを導入する際のポイントとして、以下の3つが挙げられます。
- 自社の課題を明確化する
- 社内教育を進める
- RPAとの連携を検討する
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
自社の課題を明確化する
生成AIの活用方法を決めるため、自社の課題を明確化します。業務フローを詳細にマッピングし、各プロセスのボトルネックを特定しましょう。プロセスの理解により、AIが能力を発揮できる箇所を特定しやすくなります。
例えば製造業では、製品の製造から出荷までのプロセスを分析し、自動化できる部分を見極めます。解決すべき課題や自動化できる作業を明確にすることにより、不要なツール導入の防止にもつながるでしょう。
社内教育を進める
生成AIの活用により、従業員の役割や業務内容が大きく変わる可能性があります。従業員が新しい技術を理解し、効果的に活用するための環境を整えなければ、効率化は実現しません。そのためには、生成AIや自動化ツールの操作方法とともに、業務プロセスとのかかわり方を理解するための教育が必要です。
また、生成AIは情報漏洩や著作権侵害、誤情報の出力などのリスクも存在します。AIで扱うデータを明確にする、出力された情報は担当者が必ず確認するなど、リスクを抑えるルールを設けましょう。
事前に社内教育を徹底し、担当者全員のAIリテラシーを高めることで、適切な運用につながります。
RPAとの連携を検討する
生成AIは、RPA(Robotic Process Automation)ツールとの連携が有効です。RPAとはパソコンで行うマウス操作やキーボードの入力などの定型作業を自動化できる、ソフトウェアロボット技術です。
転記作業や情報収集、データ整理、資料の作成など、手順が決まっている業務を自動化できます。例えばメール返信であればRPAがメールを取得し、生成AIがその内容を読み込んだうえで返信する文章を作成、RPAがメールを送信するといった連携が可能です。
生成AIとRPAを組み合わせることにより、自動化の範囲が広がり、より高度な業務に対応できます。
生成AI活用における注意点

生成AIの活用にはリスクが存在します。リスクを回避するためには、以下の2点について注意する必要があります。
- 内容の正確性を確認する
- セキュリティリスクに配慮する
ここでは、それぞれの注意点について解説します。
内容の正確性を確認する
生成AIが生成した情報は、すべてが正確とは限りません。内容が間違っていたり、情報が古かったりするケースもあります。学習データが偏っている場合、出力結果に偏りが生じる場合もあります。
そのため、生成された文書やデータ分析結果の内容については、担当者が必ずファクトチェックすることが大切です。生成AIは、あくまで補助的なツールであることを理解したうえで使用しましょう。
セキュリティリスクに配慮する
生成AIへの指示に入力した情報は、学習データとして利用される可能性があります。学習データが外部で使用された場合、情報漏洩につながる恐れがあります。
そのため、業務で利用する場合は、セキュリティ基準を満たしたツールの選定が必要です。生成AIの活用が、情報漏洩やプライバシーの侵害につながらないよう、取り扱いに関するルールを設けておきましょう。
生成AIで業務を自動化し企業成長につなげよう

生成AIとは、文章や画像、音声などのコンテンツを自動で生成する人工知能の技術です。生成AIを活用すれば、文書・資料作成やスケジュール管理、問い合わせ対応など多岐にわたる業務での自動化・効率化が期待できます。自社の課題を把握したうえで、適したツールを導入しましょう。
なかでも「CELF AI」はRAGを活用した問い合わせメール自動作成やAI-OCRを活用したアンケート文字の認識・データ化など、業務の効率化をはかれるAIアプリを専門知識がなくても作ることができます。さらに、CELF本来のExcelライクな表計算機能と生成AIを組み合わせることで、連続したいつもの業務フローに生成AIを組み込み、データ加工から集計・分析までをワンストップで業務を自動化できるのが大きな特長です。
CELF AIのWEBサイトでは、サービス特徴のほかに、「生成AIビジネス活用講座」や各種動画を無料でダウンロードできますので、ぜひ活用してみてください。
生成AIビジネス活用講座を無料でダウンロード(CELF AIのWEBサイトを見る)