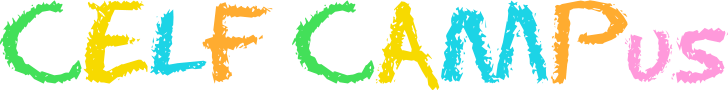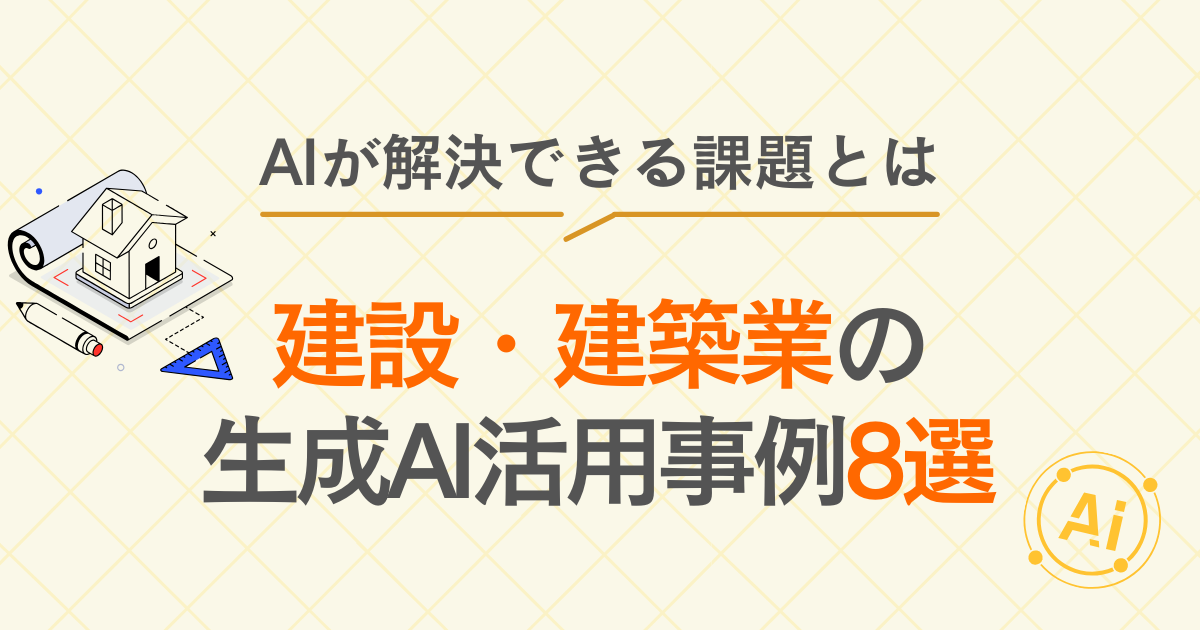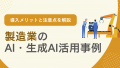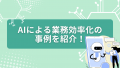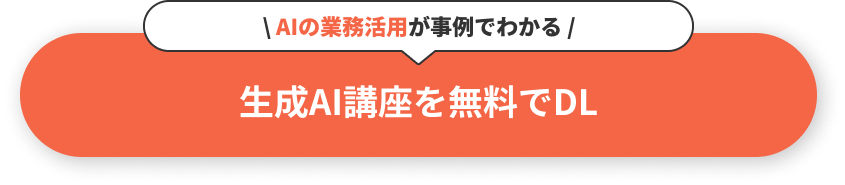生成AIは、文章や画像を自動生成するだけでなく、学習したデータをもとに最適な判断や提案を行える技術です。建設・建築業に導入することで、設計や予算作成、現場管理といった幅広い業務を効率化できるほか、人材不足や安全性確保といった業界特有の課題解決にもつながります。
本記事では、建設・建築業における生成AIの具体的な活用事例を8つ取り上げ、導入によって得られるメリットや解決できる課題を解説します。
建設業のAI活用状況
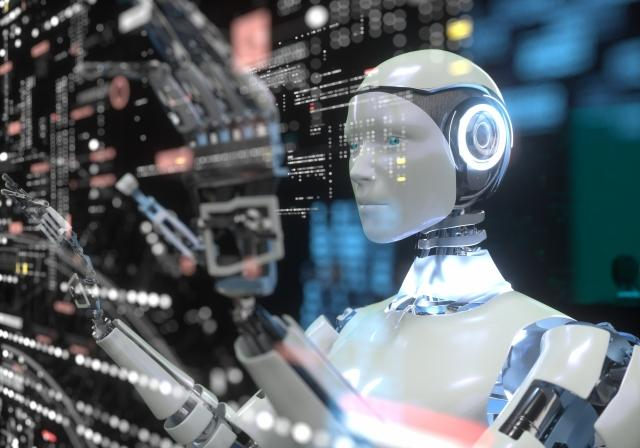
建設業はAI登場以前から多様な機材やソフトウェアを導入してきました。建築物は規模が大きく複雑であるため、特殊な機材や専用ツールを取り入れながら生産性向上を図ってきた経緯があります。
一方で、建築物は一つひとつがオーダーメイドの「一品生産」であるため、IT化を進めても大量生産のような効率化が難しいという課題を抱えています。
こうした状況の中、帝国データバンクが2024年に実施した調査では、建設・不動産業におけるAI活用割合はわずか9.4%にとどまり、全業種の中で最も低い水準でした。しかし導入した企業の約9割は効果を実感しており、AIが課題解決や生産性向上に寄与する可能性は高いと考えられます。
建設業界が抱える課題

建設業界は社会インフラを支える重要な産業である一方で、次のような深刻な課題を抱えています。
- 少子高齢化による人材不足
- 超過労働
- 安全性の確保
建設業界の就業者数は1997年をピークに減少し、35.9%が55歳以上と高齢化が進んでいます。また、労働時間は全産業平均より約90時間長く、週休2日制を確保できない現場も多い状況です。さらに、死亡災害の33%が建設業に集中しており、安全性の確保も喫緊の課題です。
建築業界は、この3つの課題が相互に作用し、業界自体の持続的発展を妨げています。
参考:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」
参考:国土交通省「建設業における安全衛生をめぐる現状について」
建設業においてAI・生成AIができること

AIは、大量のデータをもとに学習し、最適な回答や判断を提示できる技術です。その中でも生成AIは、新しいテキストや画像などのオリジナルコンテンツを生み出せる点に特徴があります。
それぞれの技術は、建設業界において、次のような業務で活用できます。
- 設計業務
- 予算作成業務
- 工事計画の作成・管理
- 危険予知
- 人材育成
設計業務
建設業界でAIを活用することで、図面作成や修正作業の大幅な効率化が可能です。過去データを学習して最適な構造や材料を自動提案し、3Dモデルやイメージ図も即時生成できます。
チームやクライアントと完成像を共有しやすくなるので、不具合の早期発見も進み、合意形成を早められます。
さらに過去のミスを学習して再発を防ぎ、設計精度と生産性を同時に高められる点も強みです。AIの活用はコストを抑えリードタイムを短縮できるため、複数案件を並行する企業にとって心強い武器となります。
予算作成業務
AIによって予算作成業務も、正確かつ素早く行えます。AIは過去の積算データや市場価格の推移などを分析し、将来的な単価を予測するのが得意だからです。
例えば、鉄骨など建材の価格変動や、地域ごとの労務費の違いを自動的に反映させ、現実に即した見積もりを作成できます。
また、AIは入力や登録といった付随作業も自動化でき、人為的ミスの削減や業務スピードの向上も可能です。AIの予測と自動化機能により、コストの最適化と資源の有効活用が実現できます。
工事計画の作成・管理
AIや生成AIを導入することで、過去の工事データや資材調達の履歴、さらには天候など外部要因を分析し、最適な作業工程を立案できます。現場の進捗もリアルタイムで把握できるため、問題が生じた際は即座に計画を修正するなど、柔軟な対応が可能です。
また、従業員の稼働データをもとに労働時間を把握・管理できるため、長時間労働の抑制や働き方改革にも活用できます。結果として、工事計画や管理業務の負担を減らし、現場全体の効率と労働環境を改善できます。
危険予知
AIの活用によって、建設現場で起こりうる転落や挟まれ事故などの労働災害を未然に防ぐ取り組みが可能です。AIが過去の事故データや現場の稼働状況を分析することで、作業員が現場に入る前に注意喚起を行ったり、安全性を高めるための対策を講じたりできます。
また、危険性の高い高所作業や重量物の取り扱いなどは、AIを搭載したロボットや自動化機械に任せることで、人的リスクを大幅に軽減することも可能です。
人材育成
AIを人材育成に活用すれば、従業員の習熟度や得意分野を分析し、個々に最適化された育成プログラムを自動生成できます。
例えば、施工技術や安全な作業手順をシミュレーション形式で学習できるAIトレーニングを導入すれば、従業員は実際の現場に近い環境で効率的にスキルを習得できます。これにより、教育にかかる時間を短縮しつつ、知識や技術の定着率を高められる点が大きな利点です。
また、ベテラン作業員のノウハウを教材化することで、経験に依存した指導を標準化できる点も大きなメリットです。
建設・建築業の生成AI活用事例

ここからは、建設・建築業における生成AI活用の事例として、次の8社を紹介します。
- 秋津道路株式会社
- 鹿島建設株式会社
- 株式会社大林組
- 安藤ハザマ
- 西松建設株式会社
- BRANU株式会社
- 鉄建建設株式会社
- 池田建設株式会社
1.秋津道路株式会社:労働時間管理の効率化を実現
秋津道路株式会社はAIによって労働時間管理の効率化を実現しています。
従来はFAXで送られる日報を担当者がExcelへ入力して集計しており、月10時間以上の作業負担が課題でした。さらに残業時間を即時に把握できず、2024年からの時間外労働の上限規制への対応も懸念されていました。
そこでAIを使った新システムを導入することで、労働時間データをリアルタイムで共有できるようにし、労働時間管理の効率化を成功させています。また、残業アラート機能も加えることで、法令遵守も強化しています。
2.鹿島建設株式会社:従業員を対象に専用対話型AIを運用
鹿島建設株式会社は従業員約2万人を対象に、自社専用の対話型AIの運用を開始しました。
実際の利用シーンは、情報収集や分析、企画書や議事録、メール文の作成、外国語の翻訳やプログラミングまで多岐にわたります。従業員からは「1日がかりのコーディングが数十秒で完了した」という声も上がっており、導入効果は非常に高いと言えるでしょう。
ChatGPTなどの外部公開型サービスは情報漏洩のリスクがありますが、自社専用のAIを用意することで、安心して利用できる環境を整えています。
参考:鹿島建設株式会社「グループ従業員2万人を対象に専用対話型AI「Kajima ChatAI」の運用を開始」
3.株式会社大林組:建築設計業務の効率化を実現
株式会社大林組は、米国の研究機関と共同で、建築設計の初期段階を効率化するAI技術を開発しました。この技術では、建物の形状を記したスケッチや3Dモデルを入力すると、複数のファサードデザイン案を瞬時に生成できるのが特徴です。
さらに、この技術は設計用プラットフォームとも連携しており、生成されたファサード案を立体的な3Dモデルに変換することも可能です。これにより、ボリュームデザインと外観デザインを一気に検討でき、画像だけでは伝わりにくい立体的な情報を交えて議論を進められるようになりました。
参考:株式会社大林組「建築設計の初期段階の作業を効率化する「AiCorb®」を開発」
4.安藤ハザマ:建設分野専門の生成AIを導入
安藤ハザマは独自の生成AIを導入し、技術伝承と業務効率化を進めています。燈株式会社と連携し、施工計画書や技術文書といった社内データを学習させることで、建設現場に直結する高精度な回答を可能にしました。
従来の汎用AIでは得にくかった専門性を補い、回答根拠の文書を明示する仕組みにより業務判断の信頼性も高めています。これにより若手社員の育成を支援すると同時に、ベテランの知見を有効活用して知識共有を促進しています。
参考:安藤ハザマ「建設分野に特化した生成AIの社内運用を開始」
5.西松建設株式会社:生成AIをコスト予測に活用
西松建設株式会社は、資材価格や人件費の変動が激しい中、AIを導入して建設コスト予測の精度向上に取り組んでいます。AIは統計データや市場動向を分析し、将来の価格変化を予測するとともに、その根拠も提示できるため、経営判断に納得感を持たせられる点が強みです。
事実、同社ではAI導入によって、資材物価指数や鉄筋・鋼材価格の推移を予測し、見積もりや入札の段階でコスト上昇リスクを考慮した判断を実現しています。価格上昇が予測される資材を先行発注するなど、収益性を確保する仕組みづくりに役立っています。
参考:xenoBrain(ゼノブレイン)「建設業界の物価変動を経済予測AIで先読み」
6.BRANU株式会社:ChatGPTを活用したサービスを提供
BRANU株式会社は、建設業界のDX推進を支援するため、ChatGPTなど生成AIを活用したコンサルティングサービスを開始しました。
このサービスは、5,000社を超える支援実績をもとに、中小建設企業の経営課題に合わせた伴走型のサポートを行うのが特徴です。AIを活用して業務フローの整理や業務選定、プロンプト設計の支援に至るまで幅広く対応し、ドキュメント作成やマーケティング業務の効率化など定型業務の自動化を実現します。
事実、BRANU株式会社自身がAI導入によって32%の社内業務削減を見込んでいます。自社で運営実績のあるノウハウをコンサルティングに活かし、さらなるビジネスを構築している好例です。
参考:BRANU株式会社「「ChatGPT」を活用したDXコンサルティングサービスを開始」
7.鉄建建設株式会社:規制帯管理の安全性を向上
鉄建建設株式会社は、高速道路工事で欠かせない規制帯管理の効率化に向けてAIを導入しています。従来は無線や電話で確認作業を行っていたため、現場管理者に負担が集中し、業務も煩雑でした。
新システムでは規制情報を一元管理し、カメラ映像や位置情報をチャットから即座に呼び出せるようになりました。結果として、現場確認の時間が1日60分から3分になるなど、大幅な時間短縮に成功しています。
さらに、報告業務も自動化され、精度向上と転記ミス防止を実現しています。
参考:鉄建建設株式会社「IoTと生成AIで高速道路リニューアルプロジェクトの安全管理を革新!~MODEと協業の実証実験成果~」
8.池田建設株式会社:AIアプリでマンション工事を効率化
池田建設株式会社は、マンション建設現場の効率化を目的にAIアプリを導入しました。従来は工事写真の整理や報告資料の作成に膨大な時間がかかり、担当者の大きな負担となっていました。
AIアプリの導入により、写真整理や図面との紐づけが自動化され、1フロアで十数時間かかっていた作業は、3分の1の時間に短縮。打ち合わせ時の情報共有もスムーズになりました。
その結果、残業削減や働き方改善を実現し、効率性と品質を両立した工事運営につなげています。
参考:スパイダープラス株式会社「検査の事前準備にBPOサービスを組み合わせて、マンション工事を効率化」
建設業の事例を参考に生成AI導入を検討しよう

建設業界では、人材不足や安全性の確保といった課題に対し、生成AIの活用が着実に成果を上げています。設計や予算作成など、幅広い分野で効率化や精度向上が進み、働き方改革や品質確保にも貢献しています。
ただし、導入にはコストやセキュリティ対策が欠かせず、従業員の理解を得ながら段階的に進めることが重要です。建設業界で多くの実績がある「CELF」のオプションサービス「CELF AI」は、初期費用なしで月額1万7,500円(税抜)~利用でき、低コストながらしっかりとしたセキュリティも備えています。さまざまな業務で活用できるのも魅力です。
「CELF AI」では、自分たちでAIを組み込んだアプリを作ることができます。たとえば、PDFや画像から自動でデータを読み取るOCR機能を使ったり、社内にある情報をもとにFAQを作ったりできます。さらに、氏名や住所の分割など、Excelでは手間がかかる作業も簡単に自動化できます。
操作はExcelに似ているので、今のやり方を大きく変えずに導入でき、現場でもスムーズに使い始められるのが嬉しいポイントです。
まずはCELF AIのホームページで無料公開されている「生成AIビジネス活用講座」を参考に、自社に適した導入方法を検討してみてはいかがでしょうか。
生成AIビジネス活用講座を無料でダウンロード