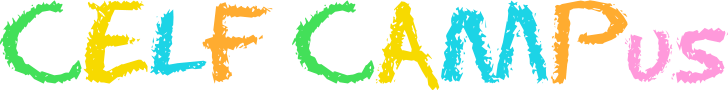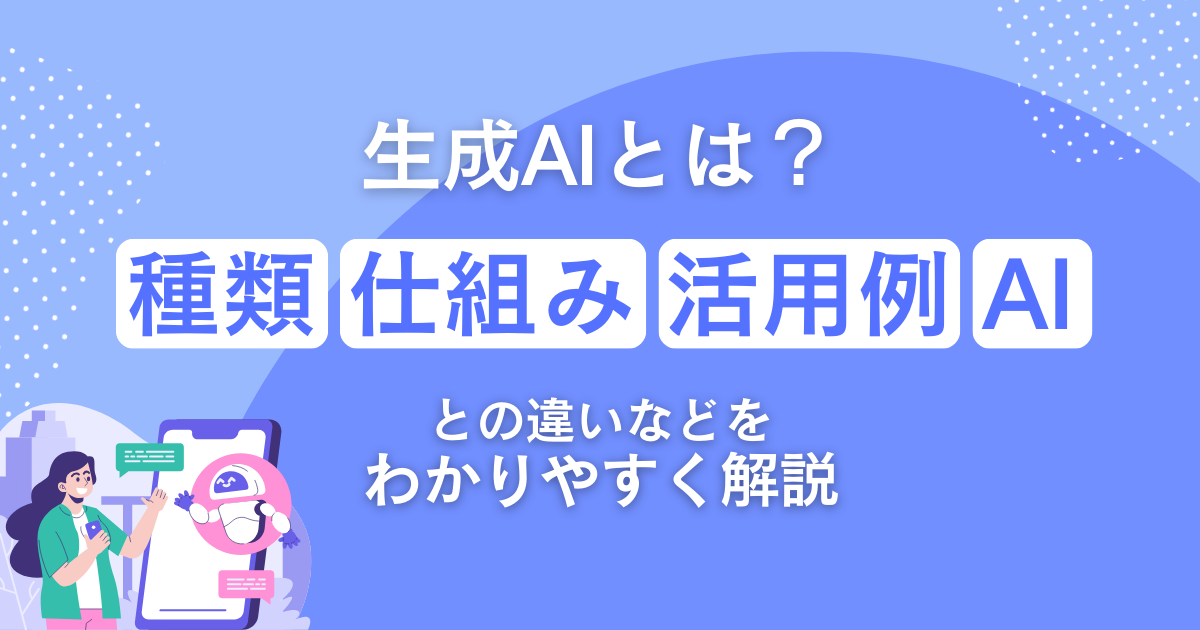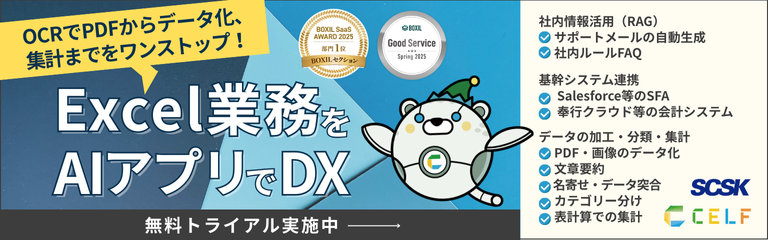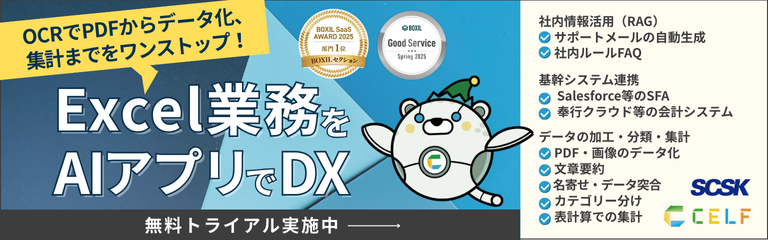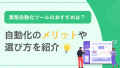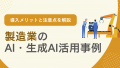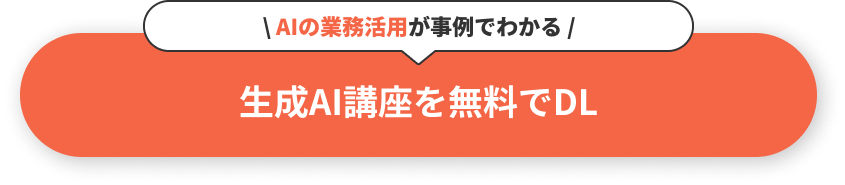生成AIとは、学習データを活用してオリジナルのコンテンツを生成する人工知能です。テキストや画像、動画、音声といったコンテンツを自動で生成できます。業務効率化やアイデアの創出ができ、顧客満足度の向上にも役立つのがメリットです。
本記事では、生成AIの概要や仕組み、種類、活用するメリット・デメリットを解説します。
生成AIとは?簡単に説明
生成AIとは、機械学習に基づいて学習したデータを活用し、オリジナルのコンテンツやアイデアを生み出す人工知能のことです。「ジェネレーティブAI」とも呼ばれます。
テキストや画像、動画、プログラムのコード、楽曲など、幅広いクリエイティブなコンテンツを生み出します。
ここでは、生成AIの仕組みや従来のAIとの違いを解説します。
生成AIの仕組み
生成AIは、深層学習(ディープラーニング)により、人が作り出すようなデジタルコンテンツを作り出します。深層学習とは、人間の神経細胞の仕組みに基づくニューラルネットワークを用いた機械学習の1つです。
与えられた大量の学習データを読み込み、「プロンプト」と呼ばれる指示を与えると、AI自身が最善の回答を見つけてオリジナルのコンテンツを創造します。
関連記事:生成AIのプロンプトとは?書き方のコツや事例・テンプレートをご紹介
従来のAIとの違い
生成AIと従来のAIは、オリジナルコンテンツを生み出すか否かが大きく異なります。従来のAIは、学習済みのデータの中から適切な回答を見つけ、該当するものを提示するという仕組みです。
これに対し、生成AIは学習したデータからオリジナルコンテンツを生み出すことが特徴です。AI自身が自ら学習し、これまでは人間しかできなかった「0から1を生み出す」作業を行います。
関連記事:AIエージェントとは?生成AIとの違いや活用方法を紹介
生成AIが注目を集める理由
生成AIが注目される背景には、2022年11月に米OpenAI社が「ChatGPT」を公開したことがあります。これにより、一般ユーザーでも高度な文章生成や対話が可能になり、生成精度の劇的な向上が広く認識されました。
使いやすさと高精度を兼ね備えたことで、ビジネスや教育、クリエイティブ分野など、さまざまな場面で生成AIへの関心が高まっています。
生成AIの種類と代表的なサービス
生成AIは、大きく次の5つに分けられます。
| 種類 | 特徴 | 代表的なサービス |
| テキスト生成 | 質問や指示を入力すると、回答となるテキストを生成する | ・ChatGPT(GPT-5) ・Claude 3.5 Sonnet |
| 画像生成 | 簡単な指示を入力すると、オリジナルの画像データを生成する | ・Gemini 2.5 Flash Image ・DALL·E 3 |
| 動画生成 | 画像やテキストの指示を入力すると、イメージに沿った短い動画を生成する | ・Runway Gen-4 ・Firefly Video Model |
| 音声生成 | 人間の音声データを入力して学習させ、新たな音声を生成する | ・Stable Audio 2.5 ・Step-Audio 2 |
| コード生成 | プログラムコードやスクリプトを生成する | ・GPT-5 Codex ・Qwen3-Coder |
ここでは、各生成AIの特徴と、代表的なサービスを解説します。
テキスト生成
テキスト生成では、質問や指示を入力するとAIがその内容を解析し、回答となるテキストを自動生成します。
人間が書いたような自然な文章を生成するほか、スムーズな対話が可能です。
代表的なサービスには、アメリカのOpenAIが開発した「ChatGPT(GPT-5)」や、Anthropic社が開発した生成AI「Claude」の最新モデル「Claude 3.5 Sonnet」などがあります。
画像生成
テキストによる簡単な指示文を入力すると、オリジナルの画像データを自動生成します。これまでは専門的なスキルと時間が必要だった画像の制作も、画像生成AIの登場により、わずか数十秒程度で誰でも高品質の画像の生成が可能になりました。
画像生成のサービスは、Googleが開発した最新の画像生成・編集モデル「Gemini 2.5 Flash Image」や、OpenAIによるChatGPT上で画像生成ができる「DALL·E 3」が代表的です。
関連記事:生成AIアプリで画像・イラスト作成!おすすめ8選とその活用法
動画生成
画像やテキストの指示文を入力すると、イメージに沿った短い動画コンテンツを自動生成します。
動画生成は他の生成AIと比較して高度な処理が必要であり、難易度が高いとされてきました。以前は時間とコストがかかっていましたが、近年はAI技術の進化により、生成のプロセスが大幅に効率化され、音声付きで1分以上の動画生成も可能です。
代表的なサービスには、2025年3月に登場した「Runway Gen-4」や、アドビによる「Firefly Video Model」などがあげられます。
音声生成
人間の音声データを入力して学習させることで、新たな音声データを生成します。文章を機械的に読み上げるだけでなく、感情に合わせた表現も可能です。また、特定の人物の音声データを学習させ、本人が話しているような音声の生成もできます。
代表的なサービスには、Stability AIが2025年9月に発表した「Stable Audio 2.5」や、産業レベルの音声理解と音声対話のために設計されたマルチモーダル大規模言語モデル、「Step-Audio 2」があげられます。
関連記事:生成AIのおすすめ10選!画像や文章を生成するAIツールの活用法も解説
コード生成
コード生成AIは、人工知能を用いてプログラムコードを自動で作成するツールです。ユーザーの指示や文脈情報に基づいて適切なコードを生成できるため、ソフトウェア開発の作業効率を向上させ、品質の安定化にもつながります。
代表的なサービスには、OpenAIが開発した最新モデル「GPT-5 Codex」やAlibabaが開発した「Qwen3-Coder」などがあげられます。
関連記事:生成AIの種類を解説!一覧や各サービスの特徴、活用シーンを解説
関連記事:最新の生成AIツールおすすめ5選!業務効率化に活用する事例も紹介
関連記事:生成AIを比較!各サービスの特徴と選び方、おすすめ12選を紹介
生成AIを活用するメリット
生成AIは、業務の効率化やアイデアの創出など、さまざまなメリットがあります。ここでは、生成AIが具体的にどのようなメリットがあるかを解説します。
業務を効率化できる
生成AIは、従来は人が時間をかけて行っていた作業を自動化し、大幅な作業時間の短縮により業務効率化を図れることがメリットです。
たとえば、新商品を販売する場面では、キャッチコピーやメールマガジンの原稿、商品のイメージ画像、PR動画の作成といった作業がありますが、生成AIはこれら一連の作業を人間の代わりに行えます。人はAIが生成したコンテンツを確認・手直しするだけで済むため、作業効率が上がって生産性の向上や人件費の削減につながります。
事務的な作業や定型業務を生成AIに任せれば、社員は空いた時間を他の重要な業務に注力できるでしょう。
関連記事:AIによる業務効率化の事例5選!生成AIを活用するメリットも解説
アイデアを創出できる
生成AIの活用により、アイデアを創出できることもメリットです。新しい商品・サービスの開発や企画の立案などが思い浮かばないときも、いくつかの情報を生成AIに与えれば、学習した大量のデータをもとにオリジナリティのあるアイデアを得られます。
生成AIは、新しいデザインやアートを自動生成でき、デザイナーやアーティストがそれをもとにアイデアのヒントを得られます。
人がアイデアを考えるときは、知識や経験に依存しがちで、似たようなアイデアしか思いつかないこともあるでしょう。生成AIであれば、知識や経験に頼らないオリジナルなアイデアを0から創造できます。生成AIが生み出した複数のアイデアを組み合わせて、よりオリジナルなアイデアを生み出せます。
コストをかけずにコンテンツを作成できる
これまで社内や外注で行ってきたコンテンツ作成を生成AIに替えることで、コストの削減が可能です。人件費や外注費用をかけずにコンテンツを作成できるだけでなく、コンテンツ作成に携わる人材を確保できないという問題も解決します。
少子高齢化による労働人口の減少で、人手不足に悩む企業は少なくありません。生成AIは定型的な業務も自動化できるため、人手不足を解消しながら、社員はコア業務に専念できるようになり、生産性向上が期待できることもメリットです。
顧客満足度を向上できる
生成AIは、顧客満足度の向上にも役立ちます。顧客の嗜好や行動履歴などを分析し、パーソナライズされたコンテンツやサービスを提示することで、顧客満足度の向上が期待できます。リピート率を高め、顧客ロイヤルティの向上につながるでしょう。
カスタマーサポートでは、生成AIによるチャットボットを導入する企業も増えています。事前に資料を登録すれば、質問に対してAIが資料の中から回答を探し、要約して提示する仕組みです。人が行うのは既存資料を学習するだけで、手間や時間がかかりません。
オペレーターの負担を軽減しながら顧客の利便性も高め、満足度の向上を図れます。
関連記事:生成AIを導入した企業の活用事例10選!活用シーンも紹介
生成AIを活用するデメリット
生成AIの活用には、フェイクコンテンツの生成などデメリットもあるため注意が必要です。
ここでは、生成AIの利用で起こりやすいデメリットを解説します。
フェイクコンテンツを生成する可能性がある
生成AIを活用して出力された情報は、必ずしも正しいとは限りません。生成AIは学習データ内の情報の真偽を判断できないためです。学習データには、根拠のある情報だけでなく、個人ブログやSNS投稿など情報が不確かなものも含まれ、誤った情報も同じように学習してしまいます。
誤った情報に基づいて学習すれば、フェイクコンテンツを生み出すリスクがあるでしょう。
著作権問題が発生する可能性がある
生成AIが作成したコンテンツには、第三者が著作権を持つ文章やイラスト、デザインが含まれている可能性があり、そのまま使用すると著作権問題が発生する可能性があります。
生成AIの開発や学習段階で著作物を使用すること自体は禁じられていませんが、生成したコンテンツを使用する際は、著作権を侵害しないかどうかをしっかりチェックしなければなりません。
情報漏洩のリスクがある
生成AIには、情報漏洩のリスクもあります。生成AIによっては、プロンプトに含まれる情報をAIが学習し、他人への回答として転用されることもあるためです。そのような場合に個人情報や機密情報を入力すれば、AIの学習データとして用いられ、他のユーザーへの回答・出力に提示される可能性があります。
生成AIへの入力は、個人情報や企業の機密情報などを含むものは避けるよう注意しなければなりません。
生成AIに用いられるモデル
生成AIの機能は、AIの性質に応じていくつかの異なるモデル(生成モデル)によって支えられています。ここでは、生成AIに用いられている4つのモデルを紹介します。
GPT
GPTは「Generative Pre-trained Transformer」の略で、アメリカのOpenAIが開発した自然言語処理モデルです。膨大な量の文章データで事前学習を行い、精度が高く自然な文章を生成します。
GPTが活用されている代表的なサービスは、「ChatGPT」です。GPTの自然言語処理を活用して、人間が書いているのと変わらない自然な文章を作り出せます。
VAE
VAEは「Variational Autoencoder」の略で、「変分オートエンコーダ」と呼ばれるディープラーニングによる画像生成モデルのひとつです。
入力された画像データの特徴を抽出し、データを圧縮(エンコーダ)して再構成(デコーダ)し、データの性質を捉えた新たな画像を生成します。データから特徴を自動的に学習するため、人が前もって特徴を抽出する手間がなく、人が思いつかないような新たな特徴を発見できます。
たとえば、特定のイラストレーターの作品を数多く学習させることで、そのイラストレーターの作品の特徴をもつ新たなイラストを生成できます。
GAN
GANとは「Generative Adversarial Networks」の略で、敵対的生成ネットワークと呼ばれるディープラーニングによる画像生成モデルの一種です。
VAEとは画像生成の流れが異なり、Generator(ランダムに作成されたデータ)とDiscriminator(学習用の正しいデータ)という2種類のネットワーク構造を競わせ、より高度な画像を生成します。
Generatorが偽の画像を生成し、Discriminatorがその画像が本物か偽物かを判別するという仕組みで、プロセスの繰り返しにより画像の精度を高められるのです。
拡散モデル
拡散モデル(Diffusion Model)とは、学習用の画像にノイズを加え、ノイズを徐々に除去しながら元画像を再構築する生成モデルです。プロセスを何度も繰り返し、高精度な画像を生成します。
GANなど従来手法と比べて安定して高精度な生成が可能で、現在の主流となっています。
「Stable Diffusion」「DALL-E」「Midjourney」などの画像生成サービスで用いられているほか、Open AIの「Sora」やリアルタイム画像生成モデルの「SDXL Turbo」など、拡散モデルを基盤とした多様な応用が広がっています。
ビジネスにおける生成AIの活用例

生成AIは多岐にわたる分野で活用でき、ビジネスの効率化やクリエイティブ支援に大きく貢献します。
ビジネスで生成AIが具体的にどのような活用がされているか、業種別にみていきましょう。
マーケティング・広告
マーケティング・広告分野では、AIと生成AIがそれぞれ異なる役割で活用されています。AIは大量のデータを分析し、顧客をセグメント化することで効果的なターゲティングの実現が可能です。
AIのセグメントに基づき、生成AIが顧客ごとに最適化された広告コピーや画像、SNS投稿などのパーソナライズコンテンツを自動生成します。これにより、効率的に多様な広告素材を用意でき、訴求力の高いマーケティング施策を短期間で展開することが可能になります。
顧客対応・カスタマーサポート
顧客対応・カスタマーサポートにおいては、人間のオペレーターと生成AIを組み合わせた体制を構築します。単純な問い合わせやよくある質問は生成AIが即時に対応し、24時間体制でスムーズな顧客サポートを実現します。
一方、トラブルシューティングや感情への配慮が必要な複雑な問題は人間のオペレーターが担当することで、柔軟かつ質の高い対応が可能です。この仕組みにより、業務負担を軽減しながら顧客満足度の向上につなげることができるでしょう。
クリエイティブ分野
クリエイティブ分野では、生成AIが記事作成やデザイン生成、多言語展開などの作業を支援するツールとして活用されています。記事作成では情報整理から文章生成までをサポートし、デザイン分野ではアイデア出しや試作品の迅速な作成を補助します。
また、多言語対応の自動翻訳やローカライズを組み合わせることで、グローバルに展開するコンテンツ制作も可能です。これにより、クリエイターは発想や表現に注力でき、作業の効率化と質の向上を両立できるでしょう。
ソフトウェア開発・IT運用
ソフトウェア開発やIT運用の分野では、生成AIがコード生成や技術文書作成といった創造的な作業をサポートしています。
コード生成では、仕様に基づいたプログラムの自動作成や既存コードの修正提案を行い、開発効率を大幅に向上させることが可能です。技術文書作成では、マニュアルや手順書を自動生成し、運用チームの知識共有を支援します。
これにより、エンジニアは高度な設計や問題解決に集中でき、開発から運用までのプロセス全体の効率化と品質向上が期待できます。
研究・データ分析
研究・データ分析の分野では、生成AIがデータの予測や分類、可視化といった高度な分析を自動化することで、大きな役割を果たしています。膨大なデータセットを短時間で処理し、将来の傾向を予測したり、複雑なパターンを分類したりすることが可能です。
また、グラフやチャートを自動生成して結果をわかりやすく可視化できるため、研究者やアナリストはより迅速かつ的確に意思決定ができるでしょう。
従来は時間のかかっていた分析作業を効率化し、研究やビジネスの価値創出を加速させます。
業務効率化・RPA連携
生成AIは、定型的な文書作成や情報整理など時間のかかる作業を自動化し、業務効率化に貢献します。その活用範囲は広く、単なる作業の自動化にとどまらず、業務全体のフロー改善や意思決定の迅速化も期待できるでしょう。
RPAと生成AIを組み合わせることで、業務効率はさらに高まります。生成AIが文章作成やデータ処理を担い、RPAがシステム操作を自動化することで、業務プロセスをシームレスに進められます。
単なるデータ処理や定型業務の自動化にとどまらず、文章生成やレポート作成といった高度な業務まで自動化の範囲を広げられるでしょう。手作業でつなぐ必要のあった複数の工程をまとめて効率化できるため、従業員は創造的で付加価値の高い業務に集中でき、組織全体の生産性と競争力向上につながります。
関連記事:RPAとAIの違いとは?組み合わせるメリットや活用事例
生成AIを業務に活用できるCELF AI

生成AIを活用した業務効率化には、CELFのオプションサービス「CELF AI」がおすすめです。「CELF AI」では、RAGを活用した問い合わせメールの自動作成や、AI-OCRによるアンケート文字の認識・データ化など、専門知識がなくても効率化アプリを作成可能です。
さらに、CELF本来のExcelライクな表計算機能と組み合わせることで、連続した業務フローに生成AIを組み込み、データ加工から集計・分析までをワンストップで自動化できます。
CELF AIの公式サイトでは、サービスの特徴を確認できるほか、「生成AIビジネス活用講座」や各種動画を無料で利用できるため、導入前の学習や活用の参考に最適です。
生成AIを安全に活用するためのポイント

生成AIを安心して活用するためには、潜むリスクを把握し、適切な対策を行うことが欠かせません。ここでは、安全に運用しつつ生成AIの利便性を最大限に引き出すためのチェックポイントを解説します。
利用規約と法規制を確認する
生成AIをビジネスで活用する際は、各サービスの利用規約を必ず確認しましょう。商用利用の可否、データの利用範囲、生成物の著作権などはサービスごとに異なります。
また、国内外では生成AIに関する法制度やガイドラインの整備が進んでいます。
日本では2025年6月、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI推進法)」が施行され、生成AIの利用に関する法的枠組みが整備されました。AI技術の研究開発と活用を促進しつつ、リスク管理を強化することを目的とした法律です。
また、総務省と経産省は、AI活用の指針としてAI事業者ガイドラインを公表しています。生成AIの普及を受けて既存ガイドラインを統合したものです。
これらの法制度やガイドラインは、社会や技術の変化に応じて適宜改定を行うものとされています。
常に最新情報をチェックし、法令遵守を意識して利用することが大切です。
参考:e-GOV法令検索「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」
参考:総務省・経産省「AI事業者ガイドライン」
入力データ(個人情報・機密情報)を管理する
生成AIを安全に活用するには、入力データの管理が重要です。入力内容が学習データとして再利用されることで、他者への出力に反映されるリスクがあります。
そのため、個人情報や機密情報などセンシティブな内容は極力入力しないよう、ルールを設けることが必要です。
生成AIの利用にあたっては、「入力を禁止する情報」を明確に定義・文書化し、ルールとして全社に周知することが欠かせません。禁止対象としては「個人を特定できる情報」「契約書全文」「パスワードやID」など、具体例を挙げて提示することで、従業員が判断しやすくなり、情報漏洩のリスク低減につながります。
出力結果の検証とファクトチェックを行う
生成AIの活用は利便性を高めますが、誤情報や不正確な内容が含まれる可能性があります。生成AIは学習データをもとに回答を生成するため、元のデータに誤りや偏りが含まれていれば、その影響が出力結果に反映されるリスクがあるためです。
結果をそのまま使用せず、必ず一次情報や公式データと照合して検証することが重要です。
ファクトチェックを徹底することで、信頼性の高い成果物を得られ、誤った情報に基づく判断やリスクを未然に防止できます。
社内ガイドラインやルールを作成する
生成AIを安全かつ有効に活用するには、明確な運用ルールやガイドラインを整備することが欠かせません。
主に、次のような項目を定めるとよいでしょう。
- 生成AIの利用手順
- プロンプトとして入力可能な情報の範囲
- 誤作動が起きた際の対応方法
- 生成物の利用制限
- 運用体制の整備
- セキュリティリスク発生時の処理手順
定めたルールやガイドラインは、関係者に周知徹底することが求められます。
生成AIで業務を効率化しよう
生成AIは従来のAIと異なり、オリジナルコンテンツを生み出せる人工知能です。テキストや画像、動画、音声といった種類があり、指示を与えるだけで手軽に生成できます。作業を効率化してコストを削減し、アイデアの創出ができる点がメリットです。顧客満足度の向上にも役立つでしょう。
個別の作業だけではなく、現在の業務フローに課題を感じ、効率化を目指す方には、Excel感覚で業務アプリを自作できるCELFがおすすめです。
CELFは、Excelライクな見た目の業務アプリをノーコードで作れるサービスです。業務アプリによってシステム化され、データの集計・入力作業が大幅に削減できます。
さらに、オプションで生成AIを活用したCELF AIを導入することで、業務全体のフローを効率化し、集計業務も自動化できるため、意思決定のスピード向上も実現できます。
CELF AIを活用すれば、AI機能を持ったさまざまなアプリを自社で作成可能です。たとえば、OCR機能を利用してPDFや画像の情報を自動でデータ化したり、社内に蓄積された情報をもとにFAQを作成したりすることができます。また、氏名や住所の分割といった、Excelでは手間のかかる作業も自動化できるため、日常業務の効率化やデータ処理の精度向上に大きく貢献します。
日常業務の効率化に、ぜひCELFやCELF AIをご活用ください。
CELF AIのWEBサイトでは、生成AIのビジネス活用が学べる講座資料や動画を無料でダウンロードできますので、ぜひ活用してみてください。
生成AIビジネス活用講座を無料でダウンロード(CELF AIのWEBサイトを見る)