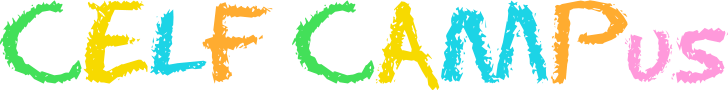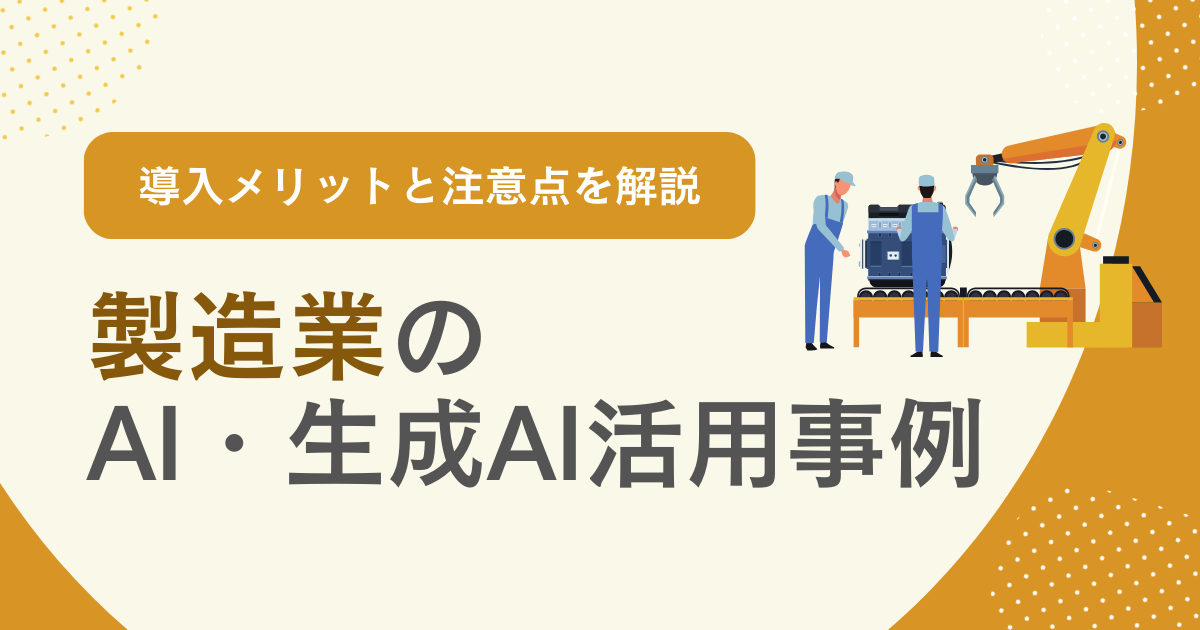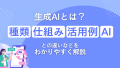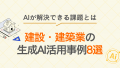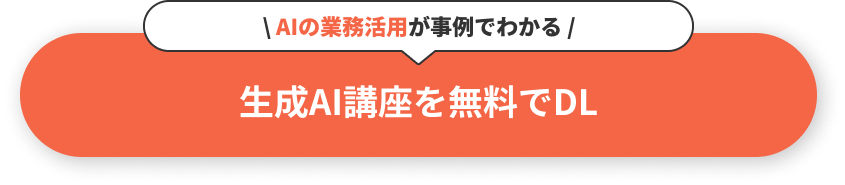AIは膨大なデータを解析して効率的な判断を行う仕組みであり、生成AIは、過去のデータを基に文章や画像などの新しいコンテンツを生み出す技術です。製造業においても、設計開発や在庫管理といった幅広い業務で活用が進みつつあり、効率化やコスト削減につながると期待されています。
本記事では、製造業におけるAI・生成AIの活用事例を紹介しつつ、導入によるメリットや注意すべきポイントも解説します。
製造業でAI・生成AIができること

製造業でAI・生成AIを活用するために、まずは次の事柄を押さえましょう。
- そもそも「AI」「生成AI」とは
- AI・生成AIを活用できる製造業の業務
ここでは、AIや生成AIの概要と製造業への活用方法を解説します。
そもそも「AI」「生成AI」とは
AIとはあらかじめ学習した大量のデータから、最適な答えを自動的に導き出す仕組みです。
一方、生成AIは創造的な成果物を生み出すことを得意としており、過去のデータに基づいて、新たにオリジナルの文章や画像を生成できます。
総務省の報告によると、製造業でIoTやAIのシステムを導入している企業は、2024年時点で全体の26.1%と少ないです。しかし、導入率に関しては前年から4.4%伸びているため、活用が着実に広がっています。
また、導入目的は「業務効率化や業務改善」が86.6%と最も多く、AI・生成AIが現場の課題解決に用いられていることがわかります。
参考:総務省 情報流通行政局「令和6年 通信利用動向調査報告書(企業編)」
関連記事:生成AIとは?種類や仕組み、活用例、AIとの違いなどをわかりやすく解説
AI・生成AIを活用できる製造業の業務
AIや生成AIは製造業において、以下のような業務に役立ちます。
- 製品設計・開発
- 資材発注・在庫管理
- 製造ラインの最適化
- 品質管理(不良品検出)
- 安全管理
生成AIを活用すれば、設計図や試作品のデザイン案を短時間で生成できます。また、従来は担当者の経験や勘に頼っていた資材発注や在庫管理も、AIが過去の需要データを分析して精度の高い計画を立てられます。
さらに、AIロボットによる組み立てやピッキングなどの作業自動化、AI搭載カメラによる不良品検出や危険行動の監視も可能です。
製造業はAIを活用することで、より業務の精度を高め、安全かつ効率的に運営を実現できます。
製造業におけるAI・生成AIの活用事例10選

ここからは、AIを活用して業務効率化などを実現している10個の事例を紹介します。
- リュウグウ株式会社
- ボッシュ
- Turing株式会社
- 水島機工株式会社
- サッポロビール株式会社
- 株式会社ニチレイフーズ
- トヨタ自動車株式会社
- パナソニック コネクト株式会社
- 東京エレクトロン株式会社
- AGC株式会社
1.リュウグウ株式会社:包装資材の研究開発をAIで効率化
リュウグウ株式会社は、研究開発における材料選定を効率化するためにAIを導入しました。
同社の開発では、多数の候補材料から最適な組み合わせを探すのに時間がかかるうえ、判断には高度な知識を要するため熟練者に業務が集中していました。
AIの導入により選定作業を数値化し、データに基づく判断が可能となったことで、未経験者でも材料選定できる体制を実現しています。その結果、開発スピードの向上と人材活用の多様化を実現し、研究開発プロセス全体の効率化につながっています。
参考:SUPWAT, Inc.「昭和22年創業・包装資材の製造/販売を行うリュウグウが「WALL」を材料業界で初めて導入開始」
2.ボッシュ:製品開発プロセスに生成AIを導入
世界的な自動車部品メーカーであるボッシュは、光学検査に生成AIを取り入れることで、製品開発プロセスを大幅に効率化しています。
検証に必要なサンプル画像をAIで生成することで、実際のサンプルを大量に用意する必要がなくなり、生産ラインの立ち上げにかかる期間を約15%短縮することに成功しました。
また、同社は自動運転技術の高度化にも生成AIを活用しています。AIが多様な走行状況を再現しつつ、車両の反応を学習することで、自動運転機能の安全性を高めています。
参考:日本のボッシュ・グループ「ボッシュ、Microsoft社と協力:より安全な道路の実現に向け、生成AIで新境地を開拓 Bosch Connected World 2024」
3.Turing株式会社:画像生成AIを自動車デザインにフル活用
Turing株式会社は、画像生成AIを活用して自動車デザインの革新に取り組んでいます。2023年には完全自動運転EVのコンセプトカーを発表し、AIを中心としたデザインプロセスにより、約1か月半という短期間で多様な成果を実現しました。
さらに、車両のエンブレム制作や新工場の名称決定といったクリエイティブ領域にも生成AIを応用しています。デザインやブランディングにAIを取り入れることで、効率性と独創性を同時に高めた事例といえます。
参考:Turing株式会社「自動運転EV開発のチューリング、AIをフル活用してデザインした「完全自動運転EV」コンセプトカーを公開」
4.水島機工株式会社:企業の課題解決にAIツールを活用
水島機工株式会社は、企業の課題解決にAIを活用しています。同社は基幹システムと周辺システムのデータ連携や受注データの処理に多大な時間がかかる課題がありました。取引先から届くデータを人手で入力するには、1日4時間近くを要することもあり、業務効率化が悪くなっていたのです。
生成AIを利用することで、基幹システムへの受注データ入力や帳票出力の自動化を実現しました。結果として、データ入力業務が約2時間に削減され、現場の負担軽減を達成しています。
5.サッポロビール株式会社:AIで在庫数の最適化を実現
サッポロビール株式会社は在庫ロスに対処するため、AIを活用した需要予測システムを導入しました。
AIが販売データや市場動向を学習し、高精度な需要予測を立てる体制を実現しています。事実、在庫ロスの約20%削減に成功しており、運用を重ねるごとに精度も向上しています。
また、在庫管理の改善は廃棄量やエネルギー使用量の低下など、環境負荷の軽減にも効果を発揮しました。今後はAIと人間の協働を強化し、より高度な需給調整を目指す方針を打ち出しています。
6.株式会社ニチレイフーズ:AIを活用し生産計画を最適化
株式会社ニチレイフーズは、工場の生産ラインにおける人員配置を効率化するためAIシステムを導入しました。食品工場は品目が多いため、従来は熟練者が時間をかけて従業員の配置調整をしており、負担の重さや属人化が課題となっていました。
導入したAIは、従業員のスキルやシフト状況を考慮して、最適な配置を自動で提示してくれるので、従来より作業時間を10分の1まで短縮することに成功しています。
また、急な欠員にもAIが瞬時に再配置を行うため、即応できる体制が整いました。この仕組みにより、フレックスタイムや時短勤務など多様な働き方にも対応可能となり、生産性を維持しながら従業員の働きやすさを高めています。
7.トヨタ自動車株式会社:磁気探傷検査にAIを活用
トヨタ自動車は、自動車部品の品質を守るための「磁気探傷検査」にAIを導入しました。微細なキズを検出するこの工程は、熟練工の技能に大きく依存しており、人材不足や作業負担の増大が課題となっていました。
当初は一般的なマシンビジョンによる自動検査を試みましたが、見逃し率32%、過検出率35%と精度が低く、実用化には至りませんでした。
そこで導入したAIソリューションにより、見逃し率は0%、過検出率も8%まで改善に成功しています。この結果、従来は2交代制で4人を要した検査工程を2人で対応できるようになり、省人化と生産性向上を同時に実現しました。
参考:シーイーシー VR+R「トヨタ自動車株式会社 様 WiseImaging 導入事例」|
8.パナソニック コネクト株式会社:労働時間を大幅削減
パナソニック コネクト株式会社は、全社的な労働時間削減を目的にAIサービスを導入しました。検索や資料作成といった定型業務から、戦略立案の基礎データ作成といった高度な業務まで幅広く活用され、日常的に業務効率化を支えています。
その結果、2023年2月の本格展開から1年間で累計18.6万時間もの労働時間削減に成功しました。AIによって従業員の単純作業にかける時間を減らし、より付加価値の高い業務へ集中できる体制を整えています。
また、社内で開発した「プロンプト添削機能」により、社員が的確にAIへ指示を出せるようになり、活用の精度が高まりました。これによって、社内の業務効率化に加えて社員のAIリテラシー向上にもつながり、知識やスキルの共有が進んでいます。
参考:Panasonic Newsroom Japan : パナソニック ニュースルーム ジャパン「パナソニック コネクト 生成AI導入1年の実績と今後の活用構想」
9.東京エレクトロン株式会社:AIカメラ導入し安全性を向上
半導体製造装置を扱う東京エレクトロン株式会社では、現場作業における指差喚呼の不徹底や誤操作が原因となるヒヤリ・ハット事例が課題となっていました。そこで、労災リスクの低減と安全意識の向上を目的に、AIを活用したカメラ監視システムを導入しています。
このシステムの特徴は、カメラ映像をAIがリアルタイムで解析し、危険行動や不安全な状態を即座に検知できる点です。例えば、保護メガネの未装着や誤った操作が確認された場合、その場でアラートを発して作業者に注意を促します。
さらに、行動の様子を動画として記録することで、後から原因を分析し改善につなげることも可能になりました。AIの導入によって、従業員の安全確保とインシデント発生時の即応体制を実現しています。
参考:HACARUS INC.「HACARUSのエッジAI ✕ カメラによる労災防止のためのシステムを東京エレクトロン テクノロジーソリューションズが導入」
10.AGC株式会社:RAG機能付き生成AIで幅広い業務を効率化
AGC株式会社は、情報検索やトラブル対応に時間を要するという課題を解消するため、生成AIを社内に導入し、運用範囲を段階的に拡大してきました。
取り組みの中心となるのがRAG機能です。RAG機能とは、生成AIが社内外のデータベースを検索し、その情報を基に回答を生成する仕組みです。従来の文章生成よりも、業務に即した応答が可能になる特徴があります。
AGCでは、開発部門が過去の設計情報を参照して新たな発想を得たり、製造部門がトラブル時に迅速に解決策を導いたりと、多様な場面で活用されています。結果として、知識の属人化を防ぎつつ業務スピードを高め、組織全体で情報を共有できる体制が整いました。現在は効果測定も進んでおり、全社展開に向けた検証が続いています。
参考:AGC株式会社「自社向け生成AI活用環境「ChatAGC」に、社内データ連携機能を付与」
製造業でAI・生成AIを活用するメリット

製造業におけるAI・生成AIの導入には、以下のような利点があります。
- 生産性の向上
- コストの削減
- 従業員の負担軽減
- 安全性の確保
- 品質の安定化
AIは膨大なデータを解析し、生産スケジュールを最適化することで設備稼働率や生産量を高め、在庫過剰や欠品を防ぎます。また、定型業務を自動化することで事務作業や残業時間を削減し、従業員が付加価値の高い業務に専念できるような体制も実現可能です。
また、カメラやセンサーによる危険検知や画像認識による微細な欠陥検出により、安全性の強化と品質の安定化にもつながります。
製造業でAI・生成AIを活用する際の注意点
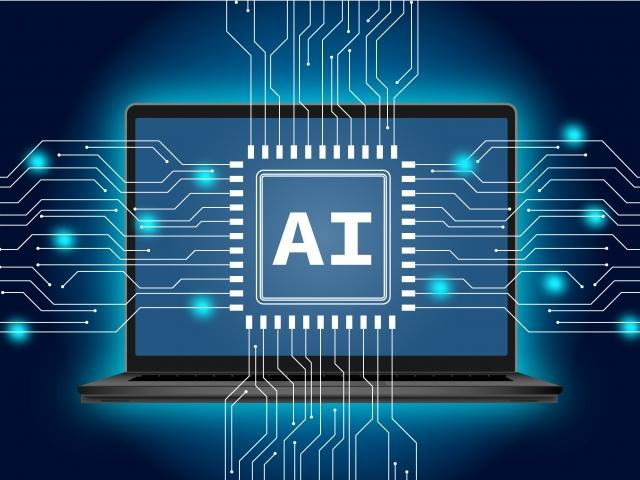
AI・生成AIの導入には多くの利点がありますが、以下の点に注意が必要です。
- 導入コストが発生する
- 効果的に活用できるとは限らない
- セキュリティリスクへの対応が必要
- 従業員の理解と協力が不可欠
導入には数十万~数百万円規模の費用がかかり、既存設備との統合や人材育成も必要です。とくに中小企業では長期的な投資回収を見据えた計画が欠かせません。
また、AIは十分なデータや明確な指示がなければ成果を出せず、運用後もテストや調整が求められます。加えて、情報漏洩や不正アクセスを防ぐためにはシステム対策に加え、従業員全体に正しい知識と意識を浸透させることが重要です。
事例を参考に生成AIを製造業で活用しよう

生成AIは製品設計や品質管理、生産計画、安全管理まで幅広く応用でき、現場の効率化と競争力向上を実現できます。ただし、導入にはコストやセキュリティ対策、従業員の理解といった課題があるのも事実です。
そのため、まずは小規模な業務改善から取り入れるのがおすすめです。製造業で多く導入されている「CELF」のオプションサービスである「CELF AI」は、初期費用なしで月額1万7,500円(税抜)~と低コストながら企業向けの高いセキュリティ性を備え、幅広いユースケースに対応できます。
CELF AIでは、AI機能を組み込んだ様々なアプリを、自分で作成可能です。たとえば、OCR機能を使ってPDFや画像からデータを自動で抽出したり、社内に蓄積された情報をもとにFAQを作成したりすることができます。また、氏名や住所の分割など、Excelでも難しい作業も簡単に自動化できます。
さらに、Excelに似た操作性を持つため、既存の業務フローを大きく変えることなく導入でき、現場の抵抗感も少ないことが特徴です。
まずは、CELF AIのホームページに無料公開されている「生成AIビジネス活用講座」を参考に、AIのビジネス活用を学んでみましょう。事例や講座を参考に、自社に適した活用方法を模索してみてください。
生成AIビジネス活用講座を無料でダウンロード