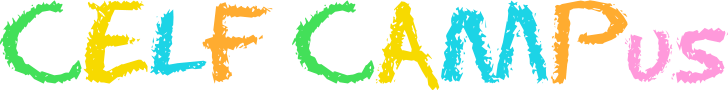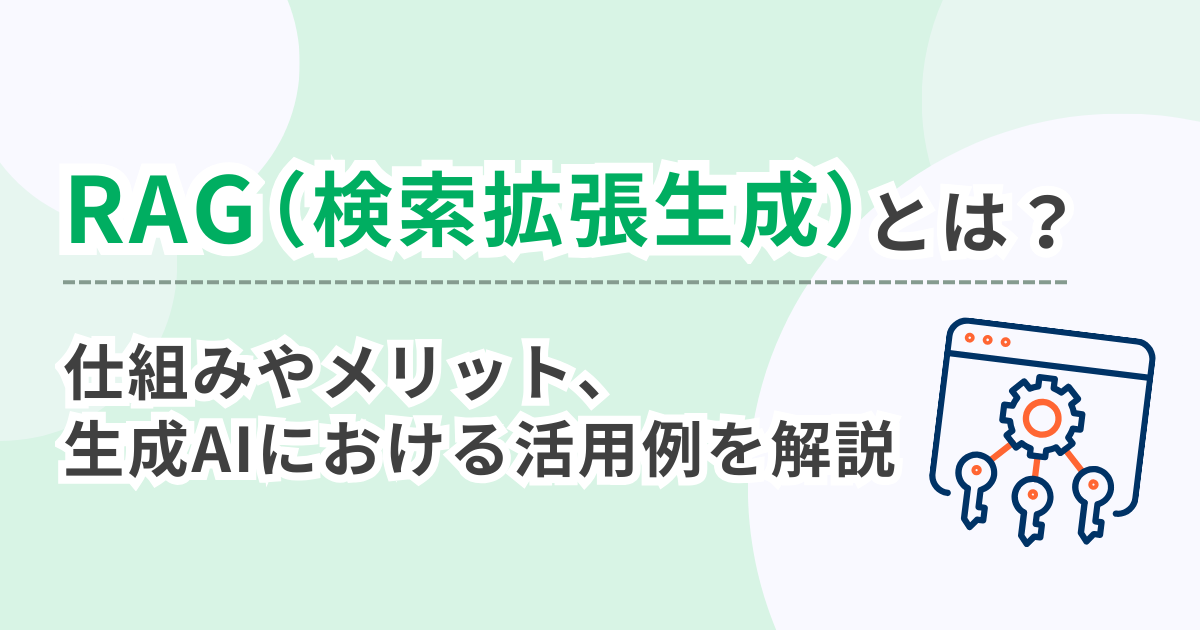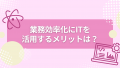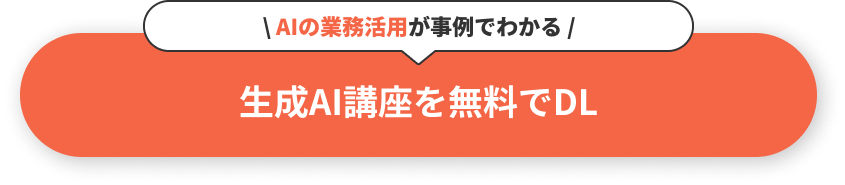RAGとは、インターネット上にはない外部の最新情報や社内情報などを生成AIに取り込み、その内容を踏まえた回答を出力できる技術のことです。
本記事ではRAGの仕組みや導入するメリットを詳しく解説するほか、活用事例をご紹介します。さらに、RAGを効率的に導入できるサービスも紹介しますので、生成AIをより効果的にビジネスに活用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
RAGとは
RAGとは「Retrieval Augmented Generation」の略称で、外部の最新情報や社内情報などをChatGPTなどのLLM(大規模言語モデル)に取り込み、回答させる技術のことです。日本語では「検索拡張生成」といいます。
ここでは、RAGが必要とされる理由やファインチューニングとの違いを解説します。
RAGが必要とされる理由
RAGが必要とされる理由は、生成AIが回答できるのが、学習しているデータに関する内容のみであるためです。生成AIの知能にあたる汎用的なLLMに、自社の社内規定や地域限定のイベントの詳細を質問しても、LLM単独では正確に回答できません。
しかし、生成AIをビジネスに活用する風潮が高まる中、社内に蓄積された情報や外部の最新情報を活用したいというニーズが高まっています。
また、生成AIが事実と反する回答を生成する「ハルシネーション」を防ぎたいというニーズも、RAGが必要とされる理由の1つです。
RAGとLLMの比較
RAGと従来型LLMには、次のような違いがあります。
| RAG | 従来型LLM | |
| 知識の更新 | リアルタイムに検索した文書を参照し、常に最新情報を反映可能 | 事前に学習したデータに依存し、知識は学習時点で固定される |
| 正確性 | 情報ソースがあるため正確性が高い | ハルシネーション発生のリスクがある |
| 専門性 | 特定業務や業界に特化しやすい | 一般的知識をメインとする |
| カスタマイズ性 | 既存データの活用で即時対応可能 | 高度な調整には再学習が必要 |
従来型LLMは事前学習された知識に基づき汎用的に回答しますが、情報の更新や特定業務への適応には限界があります。
一方、RAGは外部データを動的に参照できるため、最新かつ専門的な情報に基づいた柔軟な対応が可能です。
ファインチューニングとの違い
RAGと似たような技術に、ファインチューニングが挙げられます。ファインチューニングも、クローズドな情報を取り込む技術です。
RAGとファインチューニングの主な違いは、LLMの追加学習が必要か否かという点にあります。ファインチューニングは、学習済みのモデルに追加で独自のデータを学習させる技術です。しかし、RAGは生成AIに追加学習させる必要がありません。生成AIが情報を検索できるようにデータベースを用意し、情報をインプットします。
ファインチューニングは知識を身につけさせる仕組みであるのに対し、RAGは資料を用意しておき、生成AIがいつでも情報を参照できるような仕組みであると理解するとよいでしょう。
目的によってはファインチューニングのほうが適している場合はあるものの、RAGはファインチューニングのように追加学習のために一定の時間やコストをかける必要がなく、手軽に情報を取り込めます。
関連記事:生成AIとは?仕組みや従来のAIとの違い、活用するメリットを解説
関連記事:生成AIのおすすめ10選!画像や文章を生成するAIツールの活用法も解説
RAGの仕組み
RAGは、「検索」と「生成」を組み合わせたアプローチです。ユーザーの質問に対して、まず外部のデータベースや検索エンジンで関連情報を取得し、それをもとにLLMが応答を生成します。
それぞれのフェーズで行うことは、以下のとおりです。
検索フェーズ:必要な情報を検索して抽出する
検索フェーズでは、RAGはLLMが持っていない情報を補うことを目的に、社内情報や外部の最新情報を収集します。具体的には、以下のような流れで行われます。
- 利用者が入力欄に質問を入力する
- AIが文書やデータベースなどの外部情報を検索し、データを収集する
- 検索結果として使用するデータを取得する
インターネット上にある情報だけでなく、扱わせたい情報を別途用意して検索させることがポイントです。それにより、ハルシネーションのリスクを抑えられます。
生成フェーズ:抽出した情報を基に質問の回答を生成する
生成フェーズは、以下のような流れで進みます。
- 生成AIが利用者の質問と検索フェーズで収集したデータを基に、LLMにプロンプトを入力する
- 入力されたプロンプトを受け、LLMがテキストを自然言語処理で回答を生成し、生成AIに返答する
- LLMからの返答を生成AIが出力する
生成AIのみでは、検索フェーズで収集したデータを利用者に適切に返せません。そのため、最終的には生成AIがLLMに質問して得た回答を出力します。
RAGが解決できること・できないこと
RAGの導入によって、LLM単体では取得できない最新かつ信頼性のある情報にアクセスすることで、ハルシネーションの発生など従来型LLMが持つ課題の解決が可能です。
RAGはLLMの内部知識だけに頼らず、必要に応じて外部情報源を検索・参照することで、回答の精度や信頼性を高める役割を果たします。
これにより、常に最新の情報に基づいた出力が可能となり、回答内容の検証もしやすくなるでしょう。
ただし、RAGはLLMの学習済みモデルそのものを改変するわけではありません。あくまで外部の検索・参照機能として動作するため、LLM自体の出力傾向を根本から修正することはできない点に注意が必要です。
RAGでできること
- LLM単体では取得できない最新かつ信頼性のある情報にアクセスできる
- 外部情報源を検索・参照しながら回答できる
- 回答の精度や信頼性を高めることができる
- ハルシネーションの発生など、従来型LLMの課題を解決できる
- 常に最新の情報に基づいた出力が可能になる
- 回答内容の検証がしやすくなる
RAGではできないこと
- LLMの学習済みモデルそのものを改変すること
- LLM自体の出力傾向を根本から修正すること
RAGを導入するメリット
RAGを導入することで得られるメリットは、以下の6点です。
- 回答の信頼性が向上する
- 追加学習が不要になる
- 外部情報の更新が容易になる
- 非公開情報を活用できるようになる
- パーソナライズされた回答が得られるようになる
- コストを抑制できる
それぞれのメリットについて解説します。
回答の信頼性が向上する
RAGの活用により、回答の信頼性が向上します。外部情報を検索して回答を出力することにより、根拠が明確になるためです。
ChatGPTなどのLLM単体で回答を作り出すと元データが古かったり、そもそも学習させているデータが十分でなかったりすることが原因で、ハルシネーションが発生する場合があります。
たとえば、犬の画像のみを学習したLLMに対して馬の画像を添付して、「この動物は何か?」と確認すると、4本足という共通点のみから「犬です」と答えてしまうような場合が挙げられます。
RAGを活用すると学習済みのデータに頼らずに、信頼できる外部の情報を検索したうえで生成AIと連携させて回答を作るため、生成した根拠が明確になり、回答の信頼性が高まります。
追加学習が不要になる
RAGでは、追加学習が不要です。外部の文書やデータベース内の情報を最新化すれば、最新の情報をすぐにLLMから出力結果に反映させられます。
通常、LLMのデータをアップデートするには、最新情報を追加学習させるファインチューニングが必要です。しかし、ファインチューニングを行うためには大量の情報を学習させなければならず、多くのデータと時間を要します。
RAGは、LLMが保有するデータではなく外部情報を検索させるため、ファインチューニングを行う必要がありません。そのため、追加学習のための費用やコストが不要になります。
外部情報の更新が容易になる
RAGのメリットとして、外部情報の更新が容易になることも挙げられるでしょう。RAGはファインチューニングを行う必要がなく、外部情報を検索させるだけでLLMのデータをアップデートさせる仕組みです。
そのため、外部情報のデータを最新化するだけで、最新情報を基に回答を生成できます。たとえば、SNSフィードやリアルタイムのニュースなどに直接接続することで、すぐに最新情報を反映した回答を生成できます。
非公開情報を活用できるようになる
非公開情報を活用できるようになることも、RAGを活用するメリットです。生成AIは主に、インターネット上で得られる情報のみを根拠に回答します。そのため、自社の新製品の情報や社内規定などの情報に基づいた回答の生成はできません。
しかし、RAGはデータベースに自社の非公開情報を登録することで、インターネット上にはない情報に基づいた回答が生成できます。そのため、社内の情報やノウハウをより効率的に活用できるようになるでしょう。
パーソナライズされた回答が得られるようになる
RAGを活用することにより、インターネット上にある一般的な情報にとどまらず、パーソナライズされた回答を得られるようになります。
たとえば、自社の顧客の趣味・嗜好や購入履歴などの情報をデータベースから収集させることで、それらの情報を総合的に分析したそれぞれの顧客に最適な回答を出力することが可能です。
コストを抑制できる
RAGを活用すれば、コストの抑制にもつながります。LLMのファインチューニングには、データセットの準備や環境構築などが必要であり、コストがかかります。
一方、RAGはLLMの生成プロセスに外部情報の検索手順を加えるだけで、外部の最新情報や社内情報などを収集でき、コストを抑えられる点がメリットです。
RAGを社内に導入する手順
社内にRAGを導入する際は、次のステップを踏むことで、スムーズな導入が可能です。
- 現状の業務プロセスを明確にする
- 導入範囲を決定する
- 活用するデータを選定する
- 運用体制を確立して継続的に改善する
各ステップについて、詳しくみていきましょう。
現状の業務プロセスを明確にする
まず、RAGを導入する業務プロセスを特定するために、現在の業務フローを詳細に把握します。具体的には、どのプロセスに問題があり、どの部分の効率化が必要かを明確にしたうえで、RAGがその課題解決に適しているかどうかを検討します。
導入にかかるコストや効果も考慮し、費用対効果が高いかも確認しておきましょう。これらの分析をもとに、RAGを活用すべき業務範囲を明確に定め、導入計画を立てていきます。
導入範囲を決定する
次に、どの業務にRAGを適用するのか、導入範囲を決定します。
まず、RAGを活用する具体的な目的を明確にします。たとえば、ナレッジ共有やFAQ自動化による問い合わせ対応の省力化、迅速な情報検索による業務効率化など、達成したい成果を定めます。
その上で、特定の業務に絞って導入するのか、あるいは複数部門や全社的に広げるのか、適用範囲を検討しましょう。
活用するデータを選定する
導入範囲が決まったら、RAGで活用するデータを選定します。
まずは、RAGが参照する対象となる社内文書、データベース、Webサイトなどの情報源を特定してください。
次に、それらのデータがどのような形式(テキスト、PDF、画像など)で保管されているかを把握し、RAGが処理できる形式に変換可能かどうかを確認します。
業務でRAGを有効に活用するためには、必要な情報を正しく読み取れるデータ構造の整備が必要です。
運用体制を確立して継続的に改善する
システムの構築が完了したら、次は運用フェーズに移行します。まずは運用体制を整備し、回答精度や検索システムの応答状況などを定期的にモニタリングしましょう。
万が一トラブルが発生した際は、迅速に原因を特定し、適切な対応を行うことが重要です。
また、社員が安心してシステムを利用できるよう、問い合わせ対応窓口の設置や運用マニュアルの整備も欠かせません。
さらに、利用者からのフィードバックを定期的に収集・分析し、業務ニーズに即した改善を重ね、技術面・運用面の両側から継続的にシステムの有用性を高めていきましょう。
RAGの活用事例
RAGの活用事例は多岐にわたります。代表的な活用事例は以下のとおりです。
- チャットボットによるカスタマーサポート
- 社内の問い合わせ対応
- マーケティング・市場調査
- コンテンツ作成
- データ分析
それぞれの活用事例を確認しましょう。
チャットボットによるカスタマーサポート
RAGは、チャットボットによるカスタマーサポートで活用されます。
顧客の質問に対する答えがインターネット上にない場合でも、外部データベース内の製品情報やサービスガイドをリアルタイムで収集できます。それにより、顧客が必要とする情報を即座に提供できます。
従来、顧客の問い合わせに対しては、オペレーターが社内マニュアルやFAQを手作業で探し対応していました。しかしRAGとチャットボットの活用によって、時間がかかり、かつオペレーターの知識や経験が必要だった作業の多くの自動化が可能になりました。24時間365日対応できるため、顧客満足度の向上にもつながります。
社内の問い合わせ対応
RAGは、社内の問い合わせ対応に多く活用されています。業務マニュアルや社内規定をデータベースに登録することで、独自の社内問い合わせシステムを作成できるためです。
一般的に企業規模とマニュアルや社内規定の量は比例する傾向にあり、大企業では問い合わせ内容が書かれている資料を探すだけでもかなりの時間がかかることが少なくありません。しかし、RAGを活用すれば、従来のように担当者がマニュアルの該当部分を探し出し対処するよりも、効率的に対応できるようになります。
問い合わせ対応にあたっていた担当者は、より優先度の高いほかの業務に専念できるため、生産性の向上も実現します。
マーケティング・市場調査
RAGは、マーケティングや市場調査の業務にも活用されます。RAGで顧客の購入履歴や嗜好などの関連情報を登録すれば、パーソナライズされた商品やサービスの提案が可能です。
また、ECサイトやSNSの運用においても、最新トレンドやアップデート情報を反映した調査結果を反映しやすくなるでしょう。
コンテンツ作成
RAGは、自社製品のカタログや営業のプレゼン資料、公式サイトのブログ記事などのコンテンツ作成にも役立ちます。
自社のフォーマットを登録しておけば、フォーマットに沿ったコンテンツを作成できます。
データ分析
RAGは、各種データ分析にも役立つ技術です。たとえば、自社の生産データを登録することで、生産効率や稼働状況を分析し、製造コストの削減や生産性の向上の実現に活用できます。
また、従業員が持つスキルに関するデータや、企業への満足度などのデータを収集させ、人材マネジメントの質の向上に役立てるという活用方法もあります。
関連記事:生成AIを導入した企業の活用事例10選!活用シーンも紹介
関連記事:AIエージェントとは?生成AIとの違いや活用方法を紹介
RAGを導入する際の注意点
メリットの多いRAGの活用ですが、導入する際には以下の点に注意が必要です。
- 外部情報の精度向上が求められる
- データベースの管理にコストがかかる
- 情報漏えい対策が必要
- 回答まで時間がかかる
それぞれの注意点について解説します。
外部情報の精度向上が求められる
常に外部情報の精度を高めておかないと、RAGの持つメリットを十分に享受できません。RAGは外部情報を検索して回答を生成するため、データベースに間違いがあったり、内容が古かったりすると、期待どおりの回答を得られないでしょう。
そのため、外部情報のファクトチェックや情報のアップデートを欠かさずに行い、正確な回答が得られる状態にしておきましょう。
データベースの管理にコストがかかる
RAGは外部の知識ベースを常に最新の状態に保つ必要があり、そのための維持管理には一定のコストが発生します。
定期的なメンテナンスでは、情報の更新や誤情報の修正、新たなデータの追加といった作業が必要です。
取り扱うデータ量が増えるほど、管理負荷も比例して高まります。特に複数の部門や外部システムと連携する場合は、更新フローや責任範囲を明確に定めるなど、全体を統括する運用体制の構築が重要です。
情報漏えい対策が必要
RAGを活用する際は、情報漏えいの対策を行う必要があります。RAGに登録したデータに、秘匿性の高い企業情報や機密情報が含まれていたとしても、生成AIにそれらの情報を回答ソースとして使用してよいかの判断は行えません。結果として、意図せず機密情報が流出してしまうリスクがあることを認識しておきましょう。
情報漏えいを防ぐためには、データベース登録時における情報の選別、強力な暗号化、アクセス権の制限などのセキュリティ対策を行うことが重要です。
回答まで時間がかかる
RAGを活用すると、生成AIを単独で使用するケースよりも回答に時間がかかる場合があります。データベースから情報検索をする時間を必要とするため、データベースの規模が
大きいほど検索に時間がかかってしまう傾向がみられます。
たとえば、チャットボットによるカスタマーサポートにおいて応答時間が長いことは、顧客満足度の低下を招き、離脱の要因となりかねません。そのため、あらかじめ回答に時間がかかる可能性があることを伝えておく、データベースの情報量を適切に調整するといった対策を講じておく必要があるでしょう。
高精度のRAGを導入できるCELF
RAGの導入では回答の信頼性向上や学習コストの削減など、さまざまなメリットを得られます。一方で、正確な外部データを維持するためのメンテナンスや、情報漏えいを防ぐためのセキュリティ対策といった新たな管理負担も発生します。
こうしたRAG導入に伴う課題を解消し、高精度かつ安全な活用を実現するのが、業務アプリのためのAIソリューション「CELF AI」です。CELF AIは、ベクトル検索機能を用いた高精度のRAG(社内データ活用機能)を実装しており、あいまいな質問でも、同じ意味を理解してデータベース内の検索を行い、回答を得ることができます。
ここでは、CELF AIの概要やCELF AIによるRAGの活用事例を紹介します。
CELFとは
「CELF(セルフ)」は、業務アプリを開発するためのサービスです。専門的なプログラミング知識がなくても、現場の担当者がノーコードで業務アプリを作成できます。
Excelのような見た目と操作性で、画面設計やロジック構築を直感的に行えるのが特徴です。また、ERPや会計システムの様な基幹システムなど、社内のさまざまなシステムと連携でき、業務効率化をスピーディに実現します。
CELF AIで高精度のRAGを実現
CELF AIは、CELFにAI機能を組み合わせたオプションサービスです。専門知識がなくてもAI機能を業務アプリに組み込め、表計算と生成AIを活用して通常の業務フローをワンストップで自動化します。マスタデータからの情報補完など、基幹システムと連動したAI活用も可能です。
ベクトル検索機能により、同義語や類義語を含む語句の検索結果を得られます。これによって、高精度なRAGを実現しています。
AIの学習に使用されない設計を採用しているため、外部への情報漏洩やデータ流出を防止できます。
具体的なユースケースとしては、過去の問い合わせや問題解決データを分析したFAQの自動生成が挙げられます。蓄積されたノウハウを独自の強みとして、サポート業務やマニュアル作成に活用可能です。
CELF AIによるRAGの活用事例
株式会社プロカラーラボ様は、写真館向けにデジタル画像処理やプリントサービスを提供している会社です。学校展示写真の受託処理から納品までを担当しています。
業務の特性から「撮影内容の確認」や「閲覧期限後の再閲覧依頼」などの問い合わせが多く、撮影元の写真館でなければ対応が難しいため、案内業務には多くの工数がかかっていました。
この課題を解決できたのが、CELF AIによるRAGの活用です。まず、CELFで一元管理している「得意先一覧」や「問い合わせ履歴」などのデータを活用し、問い合わせを行ったお客様の撮影元を特定します。該当する写真館の連絡先を自動で抽出し、さらにその情報と過去の対応履歴をもとに、CELF AIが案内文や回答文を自動生成する仕組みを構築しました。
その結果、対応時間が大幅に短縮され、業務効率化と顧客満足度向上を実現しています。
RAGを導入して得られる回答の精度を高めよう
RAGは社内データを活用して生成AIの精度を飛躍的に高める技術として注目されていますが、実際に業務へ導入するには、運用しやすく信頼性の高いツールの選定が重要です。
そこでおすすめなのが、AIアプリを自分で作れる「CELF AI」です。自社のナレッジや問い合わせ履歴をもとに高精度な回答を生成できるアプリを作れるだけでなく、OCR機能を持ったアプリを作ることによって紙帳票の自動処理にも対応。セキュリティにも配慮されており、安心して業務に生成AIを取り入れたい企業にとって最適な選択肢のひとつです。
CELF AIのWEBサイトでは、サービスの紹介だけではなく、RAGについての詳しい解説や、生成AIのビジネス活用が学べる講座資料や動画を無料でダウンロードできますので、ぜひご活用してみてください。
生成AIビジネス活用講座を無料でダウンロード(CELF AIのWEBサイトを見る)