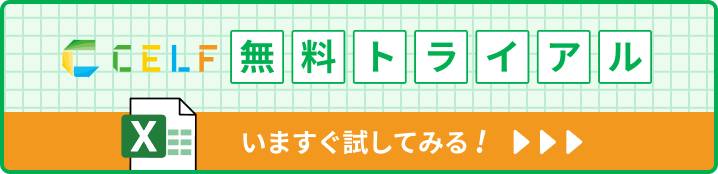2025年8月1日、東京ミッドタウン八重洲・SCSK LINK SQUAREにて「第3回 CELF開発者交流会」が開催されました。今回の交流会では「CELF AI」がテーマとなっています。交流会には全国約40名のCELFエンドユーザー・開発パートナーが集い、AIを活用した開発テクニックの共有や、問題解決に向けた開発者同士での知見共有など、活発に情報交換が行われました。ここでその模様をレポートします。

開会の挨拶:
メーカー、ユーザー、パートナーの積極的な交流を促進
開発者交流会の冒頭では、株式会社ニューイングの小林大介氏が登壇。開会の挨拶でこの交流会の目的について「メーカー、ユーザー、パートナーが集い、最新の情報や機能について語り合う場です」と説明しました。また「今回のテーマであるCELF AIについて最新の情報や開発テクニックをお伝えしますので、参加者同士で存分に語り合ってください」と話し、参加者に向けて積極的なアクションを促しました。


ライトニングトーク:
AI機能の実証実験と活用の勘所を共有
続いて、CELF AIの実証実験として4名が登壇してライトニングトークが行われ、活発な質疑応答も交わされました。ここからはライトニングトークの内容をダイジェストでお伝えします。
CELF AIを活用したAI OCRシステム登壇者:株式会社S’PLANT 磯野氏

磯野氏は、CELF AIによって注文書などの画像データからテキスト認識によって各種情報を抽出して並べ替えるシステムについて発表。プロンプトを別シートに記載することで複雑かつ長めのプロンプトによる指示も可能であることを示しました。発表では書式の異なる複数のサンプル注文書の各項目がどのように読み取られ、Excelライクなシートにまとめられていく様子がデモされました。
CELF AIを活用した住所情報の分割登壇者:株式会社ソフトエイジ 前谷氏

前谷氏は、奉行シリーズのデータ移行時に住所情報を都道府県、市区町村、番地、ビルといった4項目に分割する必要があるものの、ExcelおよびCELFの関数で対応できない場合があるため、その処理にCELF AIを活用したと言います。デモでは1つのセルに入力された長い住所情報および複数行にまたがる住所情報をCELF AIが4つに分割する様子が示されました。前谷氏はプロンプトの作成においてシンプルかつわかりやすい文章を心掛け、AIに意図を的確に伝えることが重要と強調しました。
CELF AIを活用した要員メールからの情報抽出と整理登壇者:新日本コンピュータマネジメント株式会社 塚本氏

塚本氏は、CELF AIによる「①音声データから議事録作成」「②要員情報メールからの情報抽出とリスト化」「③PDFデータからの情報抽出とリスト化」といった3つの実験を想定しました。今回のセッションでは、CELF AIは実験時点で音声データに対応していないため主に②と③について解説が進められました。デモでは、各社から届く書式の異なる要員情報メールの本文、および添付されるPDFファイルからデータが抽出され、氏名、性別、年齢などの項目に分類してリスト化される様子が示されました。
CELF AIを活用した販売実績分析アプリ登壇者:日本コンピュータシステム株式会社 早川氏

早川氏はCELF AIを活用した販売実績分析アプリの実証実験を発表しました。このアプリは、基幹システムからデータを取得し、月単位で販売傾向や翌年以降の分析を行うものであり、データの活用による仕入れ戦略の考察と在庫の最小化を目指しています。プロンプトを「経験豊富なマーケティングアナリスト」という設定にして目的や前提条件、出力内容を明確にすることで、有益な結果が得られたことが示されました。
各発表ともCELF AIの実証実験ということでさまざまな工夫が凝らされ、登壇者の具体的なプロンプトのテクニックやさまざまな試行錯誤について参加者は聞き入っていました。
ハンズオンセッション:
プロンプトエンジニアリングとRAG

続いてCELF AIハンズオンセッションが開催されました。まずはSCSKの今吉潤一氏が登壇し、CELF AIの基礎を解説。参加者に「お題」を出し、実際に手を動かしてCELF AIを活用したアプリ開発の体験を促しました。セッションは2部制で行われ、第1部では「プロンプトエンジニアリング」、第2部では「RAG」をテーマとした解説およびハンズオンが行われました。
第1部で今吉氏は生成AIの基礎とプロンプトエンジニアリングについて解説。生成AIへの指示を設計・最適化するプロンプトの作成について解説しました。良いプロンプトの特徴として、指示を細かく文章で書くこと、シンプルな表現を使うこと、曖昧さをなくして数字で表現することなどを挙げました。また、プロンプトを構造化する方法として、役割、指示、前提、出力形式などの要素に分けて書くことを推奨しました。

ハンズオンのお題は「レビュー分類アプリ」。参加者は3人グループでPCを共有しCELF AIを使ってレビューテキストの内容に応じてカテゴリ(クレーム、要望、高評価など)分類するアプリを作成しました。
第2部で今吉氏はRAG技術について説明。RAGの基礎知識に加え、CELFにおけるRAG導入時のシステム構成についても詳細に解説しました。CELF AIの場合、シートデータを参照する方法と、ナレッジを検索して必要な情報を抽出する方式を選択することで最適なシステム運用が可能であることが示されました。
ハンズオンのお題は「問合せ回答作成アプリ」、FAQのナレッジを活用してAIが質問に回答するアプリを作成。参加者はナレッジを使って回答するプロンプトを作成し、Prompt Chainingを使って正確な回答をし、サポートらしい文章を作成するアプリを作成しました。
各グループは30分ほどで議論を重ねアプリを制作。最後にアプリを完成させたグループが登壇し、その成果を発表しました。


パートナーセッション:
PCAクラウド × CELF
終盤では、「PCAクラウド × CELF」パートナーセッションが開催されました。CELFの開発パートナーであるシステムマインズ株式会社 酒井氏、ピー・シー・エー株式会社 坪井氏が登壇し、CELFと「PCAクラウド」の連携事例について紹介しました。
ピー・シー・エーは会計ソフトを中心に、給与、人事、販売管理などのソフトを提供し、近年はクラウド化を進めています。一方システムマインズは、PCAクラウドとCELFの連携を進め、導入企業に合わせたシステム開発を行っています。
酒井氏はCELFとPCAクラウドの連携方法について説明。PCAクラウドとCELF連携の大きなメリットとして「法改正対応や複雑な計算が必要な部分はクラウドアプリに任せ、周辺業務をCELFが対応することでユーザーの負担軽減と導入期間の 短縮が可能になるでしょう」と話しました。


最終セッション:
CELF最新機能の紹介と閉会の挨拶

最終セッションでは、CELFの新機能が紹介されました。SCSK 加藤氏が登壇し、「CELF BrowserAccess 」について解説。CELF BrowserAccessの最新のリリース情報について、動画を交え説明されました。

次に登壇したSCSK 福田氏は「レイアウト変更機能」について解説。CELFでのセル参照やアクション上の数式が行や列の移動に追随する仕組みや、間接参照を使うテクニックが紹介されました。

次いでSCSK 菅原氏が登壇し、AI機能についての「新機能のニーズ調査」として参加者のアンケートを募集。今後のAI機能向上の参考となることが告知されると、参加者はそれぞれ配布された用紙に自身の希望を記載していました。

そして交流会の最後に、株式会社コサウェル 萩原氏が登壇し、交流会を主催したSCSKおよび参加者に謝意を述べ、「生成AIに焦点を当てた内容で、参加者全員に刺激を与える交流会でした」と大きく評価。さらに「メーカー、ユーザー、パートナーの参加者すべてに気づきがあったと思います」と話しました。萩原氏の総括を受けて会場は大きな拍手に包まれ、交流会は無事終了しました。
参加者からは、「他社の開発者と意見交換ができ、新たな気付きや学びを得られました」「酒を酌み交わしながら、CELFの機能について深く議論できる機会は、エンジニアとして非常に有意義でした」といった声が寄せられました。また、「若手技術者にも良い刺激になる場だと思います」という感想もあり、世代を超えて交流を楽しむ参加者の姿が印象的でした。今回のイベントは、専門的な知見やノウハウの共有だけにとどまらず、参加者それぞれが新しい発見を得たり、今後の開発へのモチベーションにつながる有意義な場となったようです。皆さんがリラックスした雰囲気の中で熱心に意見を交わす様子からも、イベントの活気が感じられました。
SCSKおよびCELFアプリ開発者コミュニティは、今後も定期的な交流会の開催を計画しています。興味のあるCELFアプリ開発者の皆さんはぜひ次回の開催告知をお待ちください。