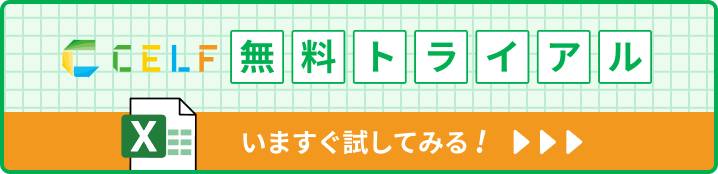CELFを活用して収支管理を統一化
データの一元管理とDB化よる経営判断の加速も実現
株式会社長谷工不動産ホールディングス

業種: 不動産業・物品賃貸業
対象部署: 分譲部門
対象業務: 収支管理業務
組織再編に伴い改善が求められた「収支管理業務」

株式会社長谷工不動産
ホールディングス
経営管理部門 経営企画部
部長 羽生 大悟氏
長谷工不動産ホールディングスは「長谷工不動産」「総合地所」といったグループ会社を束ねる中間持株会社だ。「総合地所」「ジョイント・コーポレーション(現「長谷工不動産」)」へM&Aを行い、長谷工コーポレーションで行っていた分譲マンション事業を移管するなど組織体制を再編し、2019年4月より現体制になった。
「複数の別企業が統合されたことで、業務の一部については足並みをそろえられているものの、主要な事業の後ろで動いている計算のロジックや考え方についてはまだ不十分です。それらを統一させていこうと、現在全社的な方針を掲げています」と振り返るのは、同社 経営管理部門 経営企画部 部長の羽生 大悟氏だ。
長谷工不動産ホールディングスが束ねるグループ各社は、それぞれ不動産業務を展開しているが、その予算および収支情報はExcelで管理されていた。Excelファイルのフォーマットは定まっているものの、営業担当者それぞれがファイルを編集、管理している状況のため、内容面にはばらつきがあった。また各数字の集計は手入力で作業しており、書類作成にも時間がかかっていたという。加えて会計実績についてもExcelで整理しており、メンテナンス性が悪かった。そして何より、収支管理業務全般においてExcelファイルが分散している状況だとデータの蓄積や管理が行えない、という大きな課題があった。
「グループ会社1社あたり100以上のプロジェクトを進行しています。どのプロジェクトでも、土地の購入、設計会社やゼネコンの選定、販売価格の決定など、段階ごとに収支データを各種会議に上げます。その中で、例えばスケジュールのずれ込みなどがあれば事業収支もその度に変わります。それらのデータを会議資料から読み取って逐一吸い上げていくことに経営サイドも限界を感じていました」(羽生氏)
不動産にかかわるプロジェクトなだけに、時として数十億円という規模の投資判断が要求される。だからこそ、Excelによる収支データの管理だと担当者が作成した計算式が誤っているかもしれず、その際に負うリスクも甚大だ。さらに異動や離職によって担当者が変わるとデータが散逸する恐れもあった。
「収支に関する正確なデータを得るため、そして収支を総合的に集計するために、収支データをデータベース化することが急務でした」(羽生氏)
そこでまず、分譲マンション事業における収支管理の改善が進められたのだ。
会計システムと連動したシステム開発によって
経営会議で常に最新情報が把握できるように
羽生氏が検討したのは、ローコード開発による収支管理システムの導入だった。いくつかのソリューションを検討する中、以前より付き合いのあったSIerからの提案によってCELFの存在を知り、導入を決定。2021年年末頃から外部ベンダー利用した収支管理システムの開発が開始された。
「社内での開発も検討したが、属人化を避ける意味でも、きちんとした設計書を残すような開発プロセスを経るために外部ベンダーへ依頼することにしました」と羽生氏は振り返る。
開発プロジェクトでは3カ月間のPoC(概念実証)が実施され、その後実証実験を行った後に本格的な開発、導入を開始。約1年の開発期間を経て2022年10月から本格運用が開始した。
この導入により、従来のExcelフォーマットをCELFに移管、フォーマットを一元管理することが可能になった。また、営業担当者が入力した収支データをCELFに取り込んで全物件の予算および収支データを集約することで、タイムリーに必要なデータの参照と確認が可能となり、経営会議において最新の情報を正確に把握できるようになったという。また、各種データは集計表としてCELFで自動生成できため、作業工数も大きく削減。経営サイドが求める資料の作成も、従来は1週間ほどかかっていたのが、CELF導入後は1~2日で対応できるようになった。
収支管理システムに関しても、経営統合後に進めていた基幹会計システムと連携し、各プロジェクトの会計データがCELFへ自動的に取り込まれる仕様となった。これまで担当者が入力したりCSVデータを貼り付けたりしていた手間が削減されるとともに、実績を迅速に把握することも可能となったという。
「分譲事業は、販売時期によっては年度をまたぐこともあり、収益計画が複雑になりがちです。それがCELFで収支データを管理することにより、個別のプロジェクトにおいても年度ごとの売上予測を立てやすくなりました」(羽生氏)
最大の課題であった収支データのデータベース化も実現。データ履歴を管理することで、プロジェクトに変更があった際も前のデータと比較した経営判断ができるようになった。
「データに基づいた意思決定に寄与」は経営陣からの評価も高く、グループ企業へ拡大
長谷工不動産ホールディングスでは、事業体制の再編以降同社のトップである池上一夫社長(※2025年4月1日付で副会長執行役員に就任)の掲げた中期経営計画の1つに「DXの加速による経営基盤の強化」がある。その戦略の中でも、この取り組みは高い評価を得るものとなった。
「導入のプロセスおよび成果を報告する機会があったのですが、CELFによるこのシステムの取り組みを高く評価いただきました。データに基づいた意思決定に寄与するものだとして、グループ会社への展開提案もありました」(羽生氏)
これを受け、今後はグループ内の賃貸事業や不動産管理事業においても、CELFによる同様の収支管理システム導入が進められているという。さらに、次のフェーズとしてグループ内の販売会社とのデータ連携も計画中だ。これまで販売会社から契約情報をPDFで受け取って数値を手入力する状態だったのを、CELFとの連携によって販売進捗状況を迅速に把握できるようにしたい考えだ。
羽生氏はCELFの活用拡大について「グループ全体でのデータベース化が進めば、弊社でのデータ集計もさらに容易になり、経営判断も加速化していくでしょう」と大きな期待を寄せている。会議に合わせて出される資料についてもCELFの拡充機能でビジュアル化を進め、さらなる経営判断の促進を狙っていくという。
同社のCELF導入は、根本的には経営環境の変化への対応と業務効率の改善を目指したものだが、導入によって分散しがちなデータの集約と、蓄積によるデータベース化という大きな課題も解決し、経営判断にも寄与することとなった。CELFの導入が単に業務効率化を推し進めるだけではく、企業のデータ活用基盤として大きな優位性を持つことを示す好例の1つになったと言えるだろう。